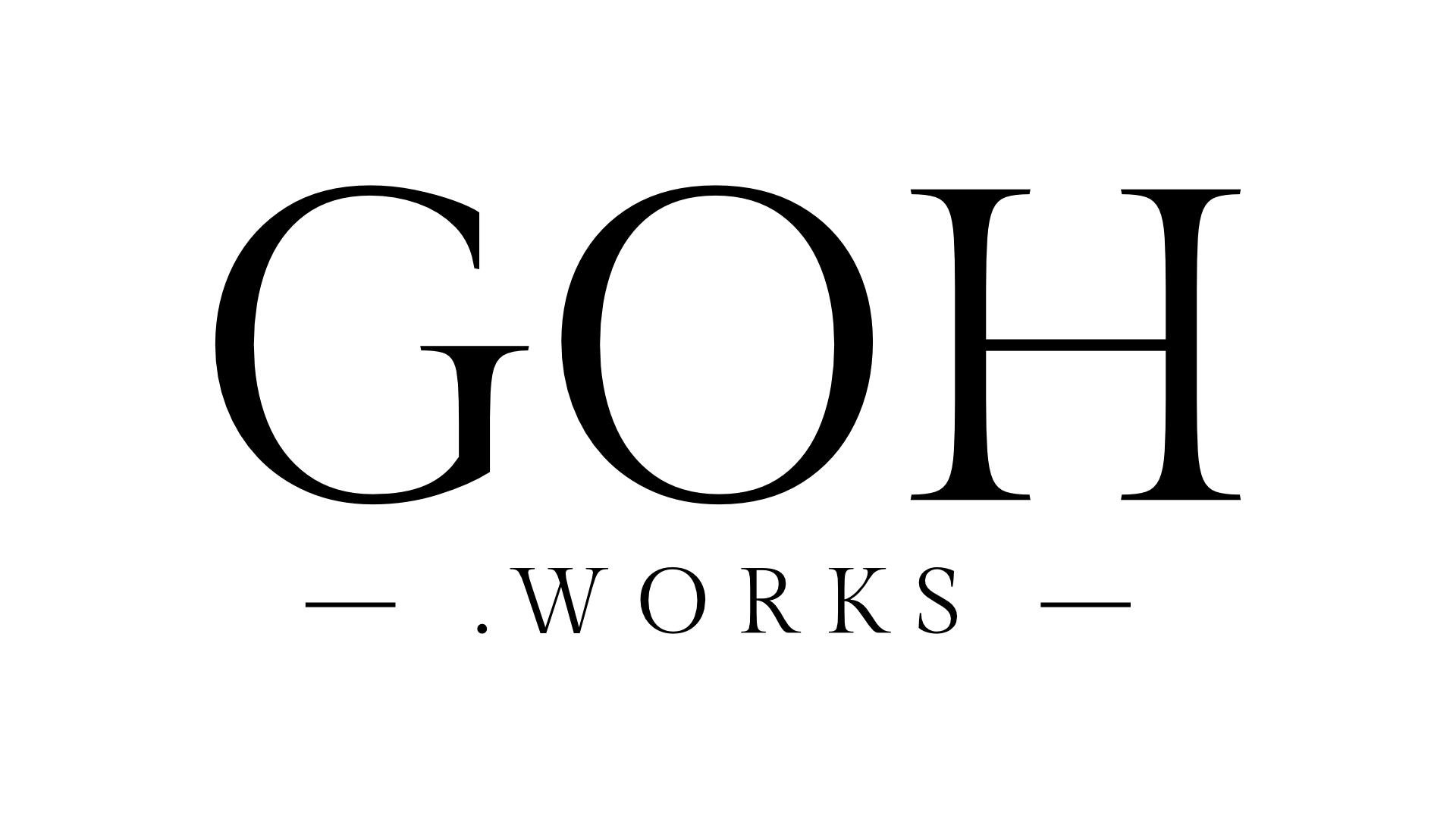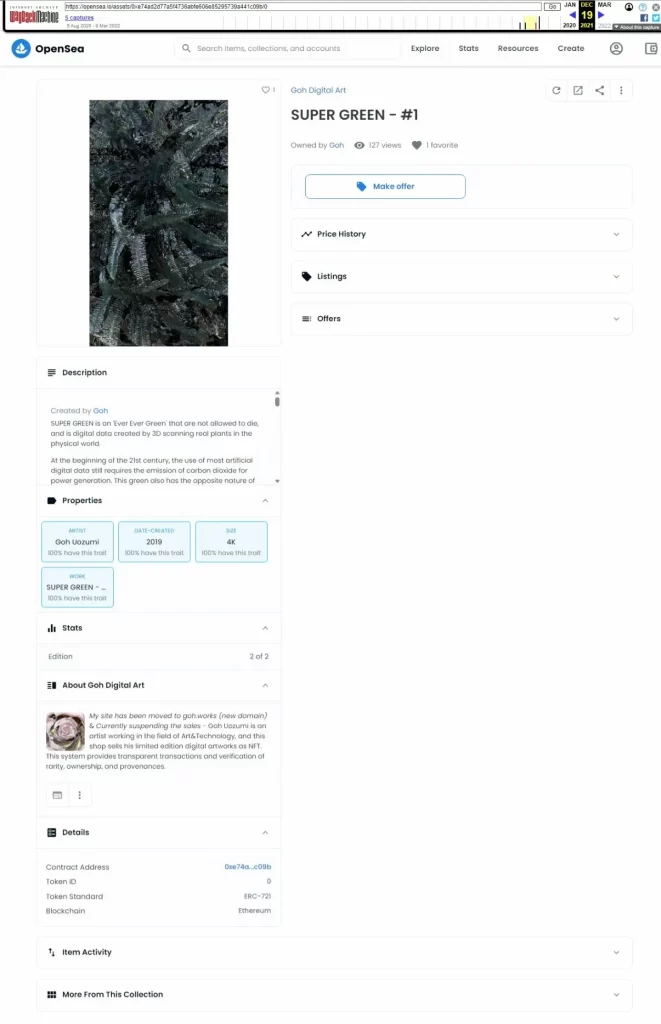2021年に追記-アートとNFTの真実
この記事は2019年に英語で公開したもので,新しいアートフォーマットを作って販売する際にリスクなどもまとめて発信することを目的としたものです.それをそのまま日本語にしたので記事内に「販売しています」等の記述がありますが,現在は販売していません.
19年の当時に僕が作ったのは,NFT が含まれるハイブリッド・エディションという作品形式です.それは NFT のみに特化したものではなかったのですが,今 NFT が話題のわりにアート関係ではまともな情報がほとんどないことや,元記事の公開から 2年が経っていて良い機会ですし,NFT 周りの事を追記して振り返ることにしました.
2021年の今では NFT の状況も変わってはいますが,根本的な問題は変わっておらず,むしろ問題を誤解して偽の解決策や誇大広告を喧伝する人が増えて,収拾がつかなくなっている印象です.
本題に入る前に,最低限の基礎知識だけ説明しておきます.
この記事での NFT というのは,ブロックチェーン上で発行する「画像作品などのデータを紐付けたトークン」のことです.トークンは,作り方次第で電子コインやチケットや証券などになれるような汎用的な証票(証書)のことで,それと紐づける作品データは画像でも動画でも音でも文字でもスクリプトでも何でも構いません(何とも紐づけない NFT もつくれます).
初めての人向けに正確ではない印象重視の説明をすると,
- まずトークンを電子コインだと想像してください.
- 次に,一枚の電子コインに「どこかのサーバー上に置いた画像データの URL 」を書き込みます.電子コインと画像はリンクしていて,コインの保有者を画像の正規の保有者とみなすことにします.
画像データは普通にコピーできますが,ブロックチェーン上で発行された電子コインは,Bitcoinなどのようにコピーして使えないようにつくられていますから,画像の正規の保有者を制限できます. - 次に,電子コインにはネット上に専用のマーケットプレイスが用意されていて,そこでオークションで売買したり取引ができます.自分の電子コインは,スマホの財布アプリで管理できて,友達に送ったり, 自分用にコレクションしたりできます.
ここでの電子コイン(トークン)は,作品の画像データの取引を便利にするための媒体といえます.たとえば他の媒体では, USBメモリに画像データを入れて油性ペンでサインして,それを手渡しなり郵送するなりで取引することもできます.電子コイン形式にすると,オンライン取引や財布アプリなどが使えて便利になるという利点があります.一方で,その裏にはいくつもの欠陥と嘘があります.
NFT(Non-Fungible Token)とは,そうした用途で使えるトークンの種類の一つです.Non-Fungible(非代替性)という意味は誤解と実態を伴わない言葉の一人歩きが多いので,一旦置いておきましょう.
NFT の役割や用途は他にも色々とありますが,この記事では「デジタルアート作品とその取引に使える仕組みとしての NFT 」に絞って書きます.(これ以降,全てのことを噛み砕いて説明は出来ないので,分からない部分は読み飛ばしてください)
NFT には作品コンテンツへの URL が書かれているだけでコンテンツの消失や改竄が起こり得ることや,アートの資産としての寿命が短いであろうこと,同一作品の重複発行などの不正が出来ること,NFT と物品作品の統合が短期的な解になるかもしれないことなどは,2019年の当時に調べた限りでは他に指摘しているものは無かったので,僕のこの記事が最初のはずです.(英語圏と日本語圏では.
元記事は簡易なものでしたが,今の NFT をめぐる混乱の中で僕の見解は価値のあるものなので,日本語版も書くことにしました.そしてついでにこの追記も書くことにしました.
この追記は元記事を読まれた人向けですので,まだの人はこの下の記事本文から読んでみてください.
これを誰が書いてるのか,書かれたことは確かなのかは,僕(アーティストのGoh)の過去の仕事の書籍や作品なども調べて判断してみてください.
僕よりもこの領域で実績と理解のあるアーティストは(少なくとも日本語圏では確実に)いないと思います.
*記事を読んで価値があれば,広告なしで無料公開しているものですから SNS でのシェアはぜひお願いします.多様な見解に触れられるようにしたり,資本力により支配的となる誇大広告に隠れた実態を明らかにするためには,独立したジャーナリズムと読者による支援が必要です.それがなければ特定の偏った情報しか得られなくなります.
有料で販売したい内容をこうして無料で公開できるのは,支援してくれる人たちのおかけです.ありがとう.
*出典は原文が参照できるようにこのページのリンクも載せてください
I just released a new hybrid edition artwork, SUPER GREEN.
— Goh *NO WAR* (@ghuzmi) September 17, 2019
It outputs one data to the following different formats
Digital Asset – 4K jpeg & its tokenized ownership as #NFT on blockchain
👉 https://t.co/xTpiwHqpIL
Physical Asset – A0 print on paper
👉 https://t.co/QZeoqIZ5QC
– pic.twitter.com/IKLH7GrPL6
アートにおける NFT
ブロックチェーンのためにあるアート
◆大まかな流れ
冒頭で,僕が2019年に記事を出した時には,NFTの構造的な問題への指摘はほとんど見つけられなかったと書きました.NFT は 19年より前からあったにもかかわらずクリティカルな指摘がそこまで遅かった理由は,アート作品における NFT の核心的な問題が「アート制作とブロックチェイン技術の両方を知っていて,かつ自分でスマートコントラクトを書いて発行から運用までシステムを動かせないと分からないこと」だからです.
この問題把握の難しさに起因した NFT 黎明期の批評性の欠落が,後の誇大広告支配の歴史への進路を定めた一因だろうと思います.
(スマートコントラクト(以降コントラクト)とは,ブロックチェーン上で動くプログラムです.この場合は,プログラムでトークンの発行量を決めたり持ち主の変更などを処理して,NFT としての機能を実現します.現在に主流となっているアート作品利用での NFT は,プログラム内に「外部にある作品データへのリンクを含めた『メタデータ』」を書き込むことで,トークンと作品を紐づけたとみなします.)
19年には既に,アート向けのものや OpenSea などの NFTプラットフォームはいくつかありました.21年の今とは違って,当時の NFT といえばゲームやトレカ用途が主であって,アート作品用途はアーティストにも投資家にもほとんど認知されておらず,しょぼいムーブメントでした.(ここでは NFT の発行から売買までできる全部込みのサービスをプラットフォームと呼びます)
今使われている NFT という言葉は,2017年の9月にEthereumのトークン規格である ERC721 の提案の際に使われたのが最初だと記憶しています(僕が当時Githubで直接見たのは,ですので,それ以前があったら教えてください).
そして17年末には,その規格を用いて,体のパーツや色などを組み合わせて無数の猫の絵柄を生成する NFT プロジェクトの CryptoKitties が登場し,Ethereum ネットワークを占有するほど話題になり「NFT は儲かる」ということが実証されます.
それに続いて 1,2年の間に,今目立っているいくつかのアート向けのNFT プラットフォームもローンチされた流れです.
(Ethereumとはブロックチェーンの一つです.17年のNFT には,Cryptokittiesと同様の CryptoPunks というプロジェクトも あって,NFTを先着順で無料配布していて一部では知られていましたが,当時はその Profile Picture NFT (Twitterのアバターに使うようなNFT)には今ほどの強い人気はなかったと記憶しています.
また,実質的なNFTのコンセプトはEthereumが発祥ではありません.後述するように他のブロックチェーンを使った「NFT 的なもの」がそれ以前からありました.)
今と同様にアーティストは,基本的には作品の画像などのコンテンツをつくって,プラットフォームが用意するフォームに情報を入力してコンテンツをアップロードするだけで NFT を発行しますから,システムの仕組みやそれが実態として何であるかを知りません.すなわち,NFT のシステムの問題への考察や対処は,プラットフォーム側に一任されます.
しかし,それら NFT のシステムを作って運用していたのは,そもそもアート畑ではなかったり,必要なはずのアートの知見やモラルがない人たちでした.
自分たちが主体となり,他人のアーティストの作品を預かるビジネスをしていながら,僕がしたようなアートにおける NFT の問題の指摘が出来ないのであれば「知見がない」ということですし,知見があったのに指摘していなかったのであれば「モラルがない」ということです.
またプラットフォーマーばかりを一方的に批判できるわけでもなく,自分の作品として NFT をそれなりに高値で販売しておきながら,システムのことを知らないアーティストの無責任さも問題でしょう. アート作品の NFT化については最近まで人気もなく認知もされていなかったこともあり,アーティスト側からの実態の検証がほとんど行われてきませんでした.
NFT に至るまでには,ブロックチェーンを「Bitcoin のようなお金」以外で使える応用用途を探すことを目的とした,様々な議論や実証実験,サービスの展開と失敗,ICO や VC による多額の資金調達といった試行錯誤がありました.(ICOは仮想通貨の新規発行でIPOみたいなもの,VCはベンチャーキャピタルです.美術関係の人はもしかしたら知らないかも)
その流れの中で,ほぼ根拠のない思い付きからアート作品の証明やデジタル化にブロックチェーンが使えると言われ始め,「カネでカネを増やす虚業だけだと揶揄されているが,ブロックチェーンにはこんな使い方もできる」と社会で存在意義を示せるものの一つして,ブロックチェーン活用を推進したい人たちからの資金援助を得つつクリエイター向けのサービスは作られていきます.
2014年頃には既に Bitcoin界隈でそういった議論と PoC があり,2017年以降に Ethereum上での商業的な成功例として,視覚作品やアバターなどの NFT領域がいくつか生まれます.その中の一つとして”NFT アート”があります.
”NFT アート”は,そもそもアートの新しい表現や取引形態の模索として,アーティストなどの創作文化に携わる人たちがつくったものではなく,デジタルメディアのアート作品の流通問題を解決するために作られた技術でもムーブメントでもありません.ブロックチェーンの応用化の流れから分岐した先の一つです.
そのためアート作品への適用には重大な欠陥があっても,ブロックチェーンの活用こそが目的であり源流であるため放置されます.「ブロックチェーンこそがアートの問題を解決する」という,事実ではなくても覆さない前提を元に全てが進みます.
ブロックチェーンのビジネスで成功したい人たちが,その正当化の口実としてアートを利用したものが”NFT アート”だと言っていいでしょう.
(「自分たちはアートから始まりアートのためにやっている」と主張する人たちはいましたが,だったらなぜNFTの不都合な真実を隠し続けるのでしょうか?)
そういった始まりと黎明期の流れが,今の歴史の土台となっています.
その上に,NFT やブロックチェーンのビジネスの受益者たちのポジショントークや誇大広告ばかりを,メディアが無批判に検証なく記事にするなどを積み重ねたことで出来上がったのが今の“NFT アート”のムーブメントなので,技術的にも資産的にも倫理的にも確かなものがない,砂上の楼閣のようになっているのだと思います.
NFT への批判的な検証が表に出てこない中で,2020年あたりから,Ethereum の主要用途であった DeFi という金融サービス領域の新鮮味が薄れ,より多くの資金や人の新規参入と,次の展開が期待され,NFT に白羽の矢が立ちます.そしてNFTプロジェクトが,それ以前からも続いていた暗号資産VCや投資家からの支援のさらなる加速により,既存のものは強化され,あるいは新たに生まれたりしつつ,「これからは NFT だ」という作られた言説と共に Ethereumコミュニティで盛り上がります.
NBAと提携した NFTプロジェクトの TopShot などを旗振りに,2021年初頭には NFT が流行する基本的な準備はできていました.それに加えて,以前から NFTプロジェクトとアートのオークションハウスとの提携が定期的に行われていたことが下地となって,同年3月にクリスティーズのオークションで Beeple氏の作品が75億円で落札されます.
これは「美術界のパトロンたちが NFT を認めた」との誤解が各メディアで報じられることで世界的な事件になり,NFT のアート利用は一線を越えます.しかし落札したのはパトロンではなくて NFTファンドのオーナーで,その実態はオークションハウスを利用した自社ファンドの資本となる NFT作品の価格操作といえるものでした.(これに関しては後章で補足します)
今年の NFTバブルに特定の黒幕がいるとまでは言いませんが,どこに資金を入れてどういった言説を流せばコミュニティが動くかをよく分かっている人たちを背後に,マクロには方向を同じくするブロックチェーンビジネスの受益者たちによる明らかな意図をもって,人為的に仕掛けられて作られたものだろうと思います.
ちなみに Ethereumコミュニティの動向を追っていた人は今年に NFT が流行ることが分かっていたようで,僕の知人は事前に仕込んで大きく儲けたと言っていました.一方でアート関係者にとっては,突然 NFT なるものが出現してバズって驚いて,権威的な機関も関わっているし金額も大きいためにアートにおいて革新的な動向だとでも思ったのでしょう.落ち着いて識者に状況を聞けば回避できたような,NFT企業や受益者たちによる嘘まみれのプレスなどをそのまま検証せずに世に垂れ流して,事実上 NFT を煽るようなことを続けてしまいます.(たとえば Twitter で以前から Dappi はフォロワー数も多く話題になっていましたが,だからといって Dappi の言い分をメディアが拡散するのは報道倫理に反していますよね.「ただ報じてるだけで中立である」なんて言い訳は普通は通用しないでしょう)
その後は,技術の適性や金融メカニズムや暗号通貨文化に疎いため,NFT企業の営業を真に受けて自分で是非を判断できない美術関係者たちが,まんまと乗せられていき,貧すれば鈍するでアーティストたちは次々と手を出していくことになりました(お金に困る以外にも話題性を欲するという意味で).自分たちが触っているものが何であるかを知らずにです.
◆ アーティストは何に加担するのか
NFT 市場の投機性から,発行者や購入者が批判されたりもしますが,彼らはただのプレイヤーに過ぎません.この投機システムの裏には,ブロックチェーン資本家や暗号資産VCなどの胴元がいて,実行主体は NFTビジネスを行う企業たちです.
そこでのアーティストは,カネと人を集めるために担がれる神輿です.
マルチ商法やMLM,ねずみ講,ポンジスキームなどと呼び方や種類がいくつかあって危険視される販売方法のどれかに,NFT のプロジェクトやプラットフォームが程度の差はあっても類似します.(どれかに該当する場合は詐欺を疑うのが一般常識です.しかし詐欺でない有用なスキームにもなり得えて,はっきりと線引きするのが難しい問題ですから,誠実に NFT を推進したいのであれば十分な議論が必要なはずです.その疑いに対して議論を開き,明確な論拠をもって説明する役割は事業者側にありますが,今までそうした例を僕は見たことがありません.)
それらの販売方法に共通するのは,既存の参入者が新規の参入者を呼び込んで増やしていけば,呼び込む側と胴元が儲かる仕組みで,ネットワークを急速に拡大させられるという性質です.それによって NFT は短期間に巨大な市場と社会的な認知を作り出しました.同様の現象として,2017年からの仮想通貨バブルが発生しました.
ここで重要なのは,販売の起点を NFT をつくる個々のアーティストではなくて,プラットフォームや Ethereum などのブロックチェーン自体へと移す見方です.
アーティストが自作品を個別に NFT にする場合は,転売時のロイヤルティを設定することで,転売数や取引価格の上昇を期待し,より多く消費する新規参入者を呼び込む直接的なインセンティヴが発生します.それだけだと,生産者が消費者に商品をより多くより高く売ろうとするだけの販売行為に見えます.悪く言えば「ババ抜き」です(自分が持つ NFT というカードのジョーカーを,発行や購入により自分が入手する際に要したコストよりも高値で他人に売り渡していき,最後にそれを持っている人が負け.自分以外にババを掴む人がいる内は購入と売却の差額分が儲かり,その逆なら損をするので,新規参入者を過剰に勧誘するインセンティヴが発生します).
しかし,たとえば Ehtereum を使う場合は,アーティストは Ethereumで使われる Ether という暗号通貨(ネイティヴトークン)を,ブロックチェーンというネットワークコンピュータの利用料の支払いのために購入する消費者になります. マーケットプレイスなどのフロントサービスでは NFT をクレジットカードで購入できることもあるため気が付かないかもしれませんが,Ether は NFT を発行するのにも取引時に動かすのにも,必ず必要になるもので,裏で誰かが購入して使用しています.また Ether は,暗号資産の投資家たちが利益を期待して多額の資金を投入している金融資産であり,発行上限もないため新規に購入する参入者を増やし続けることを求められます.
Ethereum が販売する Ether の消費者であるアーティストは,自身の NFT を販売することで新規の Ether 消費者である NFT購入者を呼び込み(多くの場合は NFT代金も Ether で支払う),その購入者は自分の NFT を次に買ってくれる新規の購入者を呼び込み…,ということを連鎖させてネットワークを拡大します.ネットワークが豊かになると大きく得をする人は種類が分かれますが,たとえば a16z のような VC から見れば,さらなる成長と一発当てることによるキャピタルゲイン回収のために次々と資金投入する NFTプロジェクトや企業を家畜だとすると,そのサービスに商品を提供するアーティストは,餌を集めるための罠みたいなものと言えます.起点を他のブロックチェーンや,NFTプラットフォームや DAOもどき に移しても,手数料や金利など利益が得られる箇所はそれぞれ違いますが,胴元へと富が集約する傾向は同じです.
詐欺とは言えなくても,こういった「ネットワークに貢ぐといえる連鎖的な消費の勧誘」にアーティストは加担すべきなのか,つまり「アートの倫理」としてどう捉えるかは議論が必要です.
「こんな作品をつくった.だから物好きな誰か買ってくれ」という普段の作品制作と販売のスキームとは明らかに違って,自律的ではなく,別の何かに隷属するために仕事をしている構造を理解し,その是非は問うべきです.スキームが違法でないかや,現行のマルチ商法に正確に該当するかどうかなどは関係ありません.
また Profile Picture NFT(アバターNFT)のような, 似たような多数の絵柄を生成して多数の NFT を発行するプロジェクトは,事実上はほとんど仮想通貨の新規発行と同じで,ユーティリティが有ろうが無かろうが,どんな無価値なものであろうが価格を付けられるスキームだと前回の仮想通貨バブルで実証されています.(ICO 詐欺,などで調べてみてください.)
さらに悪質なものは,NFT の転売時の利益を過去の保有者にも分配したり金利を付けたりする,NFT が明確な金融商品化しているもので,そのまんまネズミ講やポンジスキームだったりします.プロジェクト拡大の限界が見えた段階でプロモーターがカネを持ち逃げする実例もありますし,この辺りになってくると普通に詐欺だと思います.
現在の NFT 市場は,こういった複合的なスキームによるネットワークの急拡大の恩恵で成り立っているため,「販売方法の良し悪しと NFT自体は別」という主張は受け入れられません.どう見ても無関係ではないでしょう.
そのスキームへと人々を呼び込む神輿としてアーティストが担がれると,NFT はクリーンな印象と「アーティストのためになる」という擁護の論理が得られます.あとは「これまで収益が低かったアーティストが報われた」などと感動的な物語でも流しておけば責める方を悪者に仕立てられ,連鎖商法的な誘引スキームの議論からは関心を逸らすことができます.
アーティストは担がれているうちは気持ちいいのでしょうが,実際には誰に利用されて,何に加担し,支配されているのかを自覚した方がいいでしょう.
Twitter を見ていると分かるでしょうが,「NFT 始めました」と広告塔になり得るクリエイターが参入すると,みんなで祭り上げてご祝儀価格で購入され,メディアはそれに追随して拡散します.作品が売れたとも言えますが,NFTを宣伝する広告費を得たとも言えるのが実情だと思います.
一方で,批判は黙殺されたり(致命傷にならないものだけ流通し),シンパから袋叩きにあったり,「新しい技術についてこられない遅れた人」や「嫌儲」などと揶揄されますが,あくまで印象操作であり,そこに論拠はありません.
NFT を喧伝するほとんどの人や企業などは,デジタルメディアでの作品の市場が開かれることによってクリエイターが報われる事そのものではなく,「ブロックチェーンを使う事」を是としています.ですから NFT を使っていれば支援し,使っていなければ無価値で,批判的であれば敵と見なされます.
ほぼ同じコミュニティ化,というより「部族化」が,17年からの仮想通貨バブルの時にも発生しましたが,それと違う点はアーティストが加担者になっていることです.
揶揄には揶揄でお返ししますが,僕には NFT による部族化がつくっているのは「まるで独裁国家で政府を支持するクリエイターだけが表舞台に立てるような不自由な世界」に見えます.
とはいえ,そもそもの美術品市場自体がそれなりに怪しいことが多々あるため,NFT と相性が良かったとも言えるでしょう.
また NFT を含む暗号資産の取引には株式のような取り締まりが難しく,仮装売買やインサイダー取引などが自在にできることも,これに大きく寄与したはずです.
(たとえば NFT の市場を見たときに,「こんなレベルの絵でも売れるなら自分でもできる,自分ならもっと儲けて,大金を手に出来るのでは」と期待して参入する人も多そうですが,それらは自作自演の取引かもしれません.自分たちで複数のアドレスを作って,価格を釣り上げる取引を自作自演で行い,「こんなに高額で取引されるほど人気がある NFT だから,買って次の人に売れば儲かる」と見えるような状況をつくって,投機の参入を誘います.同じ方法が過去の仮想通貨バブルで使われました.嘘を嘘と見抜けない人はなんたら,と言うそうですが,暗号通貨の世界はまさにそれです.いちいち真に受けてはダメです.)
NFTは,ビッグテックの覇権による Web2.0 を越えた,非中央集権的な Web3.0 によるクリエイターエコノミーだとか自由な未来のためのイノベーションだとか,色々と飾り立てられています.
しかし,それは技術的な適性や問題解決の議論から導かれたものではなく,特定のコミュニティが扇動のために感情に訴えかけるように作り出したレトリックに過ぎず,実態は胴元が儲かるネットワークへの奉仕であり,支配者がこれまでとは別のものに変わるだけの集権化する世界への加担ではないでしょうか.
既に NFT市場は OpenSea が一強でほとんどの取引を占めるように中央集権化して検閲まで行われ(当然とはいえヒトラーの NFT がデリストされた),その次に台頭するのは分散的な各自販売というわけでもなく,Coinbase や FTX などの取引所のマーケットプレイスだと強く予想されます.
また現在は約17%のアドレスが Ethereum上の全ての NFT の80%以上を管理していることが明らかになっています.その占有者たちは,クジラやNFTプラットフォームや取引所などです.前者の場合は普通に富が偏っており,後者の場合は NFT の発行や購入時に取引所に資産が預けられているだけで普通によくある集中化といえるのですが,逆に見ればこれまでに無かったような分散流通はしていないということです.
状況をよく見てみると,これまで通りの普通の市場形態へと収束しており,NFT が他のデジタルメディア市場に対してどの程度の構造上の優位性を備えるのかは疑わしいです.
作品制作において,膨大な計算力を必要とする機械学習研究やメタバース運営などの大きな資本による成果に依存しなけば実現できない事は多々あるので,アーティストは完全な自立が理想であるなどと極論を言うつもりはありません.しかし NFT はただのデータ販売方法に過ぎず,それにしては過度な支配への容認を求められます.
自分の作品を NFT にしなければならない理由が僕には分からないです.これは本当にアーティストに必要なものなのでしょうか?
◆ まとめ
今日において既に,「NFT は新しくてよく分からないもの」ではありません.以前からあって問題点もそこそこハッキリしていて,技術においても法規制においても初期の暗号通貨ほど見通しが困難なわけではなく,比較的に扱いやすい類のものだと思います.
正確な情報や各分野の専門知が公開されていれば,本来は大して混乱は起きないはずです.
しかし,NFT に興味があって調べてみても,まともな情報や批判よりも NFT企業や投資家たちによるマーケティング記事ばかりが出てきて,とてもすごい新しい技術が出てきたように印象付けられはしても,自分の頭で考えるとどこか腑に落ちないはずです.そこで何が誤魔化されているのかを考えようにも,別の立場で書かれた記事が見つからなかったりします.
これはフェイクニュースとファクトチェックの関係に似ていると思います.フェイクのように正確さを求めない情報を流す側には,(全員でなくても引っかかる)カモを集めることで儲かり,かつ低コストで実行できるという利点があるのに対して,ファクトチェックには利益はほぼ無くて多大なコストがかかるだけなので,誰もやりたがりません.そのため,基本的に一方的に有利なフェイクが流布されることになります.
少なくない人が NFT に不信感を持っているのは,それが新しくて分からないからではなく,そうした異様な偏向的な状況に対してだと思います.
なぜ強い偏りが生まれて維持されているのかというと,そもそも NFT が上述した経緯で成り立っているからだと思います.全てはブロックチェーンの成功のためにある.
(余談ですが,僕は 2014年頃から暗号通貨やブロックチェーンのアート利用の動向を,自分でそれ関連のシステムを開発しながら,ずっと追い続けています.記録が残っている具体的な発表歴は,14年に日本分子生物学会でブロックチェーンを用いた監視空間の分散評価システムをmetaPhorest枠で発表,15年にフランスでDitigalChoc賞の作品としてTrustless Trust/Mk.Godを発表,16年には東京のICCで作品のNew Order/Siren Call?を発表で,この展示が日本で最初の暗号通貨と分散台帳(ブロックチェーンを含む総称)を主題にしたもので暗号通貨研究者を呼んでイベントなどもしていました(もしかしたら美術館等でない個人スペースなどで他の先例はあるかもしれません).その後は17年に現代思想のビットコインとブロックチェーン特集に論考出してたり,色々と続けています.
ですからこの記事は,ググって見つけた誰かの記事をチェリーピッキングしてる類のものではなくて,自分でやって見てきたので知ってることや考えてることを書いています.)
よくある誤解,誇大広告
冒頭で書いた,未だに続いている誇大広告についておさらいします.
1.デジタル作品の唯一性
最もよく言われている「これまでデジタル作品のデータはコピーが出来るため本物がどれか定められなかったが,NFT は本物を一意に定められるのでデジタル作品の唯一性を獲得した」という類のものは,間違いです.NFT は作品の唯一性を保証するものではありません.ちなみに作品の真正を保証するものでもありません.
まず初歩的なことですが,今一般的に使われている NFT には,作品データ自体ではなくて「データが置かれている外部サーバーのURL」が書かれているだけです.実装次第では作品データを後から改竄されたり消失しますから,作品の唯一性は得られません.19年の元記事のこちらを参照してください.
主要な NFT のマーケットプレイスでは,作品の画像データを毎回取得せずにキャッシュしたデータを表示するので,「キャッシュを表示している Opensea上では猫の NFT だと思って購入したが,裏で NFT 本体の作品への参照URL が犬の画像へと入れ替えられて,犬の NFT を購入したことになる」という事態も起こります.
代表的な Ethereumの NFT規格は自由度が高いので,この問題がどの程度対策されているかは NFT ごとに違います.
今はコントラクトが参照するメタデータ内の URL を読み込んで表示する実装が主流なので,作品データの供給に IPFS などを使っていても DNSハイジャックなどのサイバー攻撃による改竄は可能なはずで,ドメイン失効による作品データへアクセスの消失や,ドメイン乗っ取りによる作品データの改竄も起こり得ます.(https://ipfs.io/…などを使ってデータを供給していますから)
この問題は,NFTの規格を厳格化して,ゲートウェイを使わないネイティブな IPFS に皆が対応する(つまり他のデータ供給方法に対する排他的利用になる)などの対処をしなければ解決したとは言えないでしょう.
ちなみにブロックチェーンによっては,外部サーバーではなくてブロック内部に作品データを埋め込めるものもあるのですが,そうしてブロックチェーンが肥大化すると後述する寿命の問題が顕在化するはずです.
次に,上記が解決できたと仮定しても残る根本的な問題です.
ある作品のデータを,別々の複数の NFT として発行して販売できます.マーケットプレイスAでその NFT を買って唯一の作品だと思っていたら,マーケットプレイスBでも同じ作品が売っていた,ということが起こります(同一データでの重複発行).Ethereum 以外にもブロックチェーンにはいくつも種類があって,NFTを売買するマーケットプレイスもブロックチェーンごとに違い,かつ世界各国に多数あります.それらの全てを網羅して作品の重複発行を見つけることは困難です.たとえば,今インドや中国やフィリピンやフランスやイタリアなどそれぞれの地域で取引されている NFT作品のことをあなたは知っていますか?
さらに,ある作品データを一方では NFT にして,他方では同じデータを NFT ではない別の方法で販売することもできます.たとえば,NFTにした映像作品のデータを,SSDに入れて手渡しのオフラインでのプライベート販売するなどです.そうすると上述の条件よりも重複流通の発見はより困難になります.
さらに現実には,作品の権利者が複雑化したり,売買の地域の多様化や,国や言語によってはインターネット上の障壁で分断されたりします.たとえば,アーティスト本人ではない作品の権利運用組織が多国間で代理販売する場合に,内部に裏切り者がいれば秘密裏に正規であることの信用や情報を横流しして, 犯罪人引渡し条約を結んでいない国で贋作を作成し,他国で流通させるなどです.ドキュメンタリーも制作された米国でのノードラーギャラリーの贋作事件で,贋作をつくっていたPei-Shen Quian氏は中国に帰国したため捕まえられないことから分かるように,被害から贋作元を特定できても捕まらないのであれば犯罪は成功します.まず前提として何であっても贋作を売ること自体は可能ですから(人は騙されるもので,買ってしまう人はどこかにいますから),捕まることを抑止力にして犯罪を防ぎます.しかし物品の美術品を扱う場合は輸入出の都合などで犯罪の難易度が上がるのに対して,データの移動は自由ですし,NFT では作品のオリジナルデータをコピーできる上に暗号通貨のシステムですから,どうとでも出来ます.そして実行犯が分かっても他国からは逮捕できないのであれば,それ以上の捜査が出来ずに首謀者側まで辿り着けませんし,内部の協力があれば権利組織の管轄の穴をついて犯行できるので発覚しくいでしょう.犯罪のコストとリスクに対して得られる報酬を考えれば,将来に普通に起こり得ると思います(悪用されると嫌なので肝心なところを誤魔化して書きましたが,他にもアート向けで有効そうなスキームはいくつか思い付きます).
故人のクリエイターの作品を勝手に NFT にしている実例もありました.これは家族が存命であったので対処できていますが,そうでない場合は権利者が分からずに,ずっとコピーが本物として取引されていたかもしれません(この件で使われたTwinciというサービスを誰か知っていましたか?).こういった権利関係者とは無関係な第三者が,データを無断コピーして勝手に NFT にして販売することは以前から問題になっていますが,結局はそれぞれの NFTマーケットプレイスがデリストするくらいしか対処できません.
また売買する地域が,中国のようにインターネット上のサービスの多くを遮断している場合は,その内外で何が起こっているかは双方からは分からなかったり,分かるまでに時間がかかります.
こうしていくつもの条件を組み合わせていけば,不正の発見や処罰はより困難になります.「作品の唯一性を保証する」ということは,悪意のある誰かがそれを崩すことを防げなければなりません.しかし上述したように NFT では無理で,別の技術が必要だと分かるはずです.
ハックされたバンクシーの公式ウェブサイトに偽のNFT販売のリンクが仕込まれ、コレクターが340,000USDで偽物を購入した。3700万円くらいか
— Goh (@ghuzmi) September 1, 2021
防衛対策がザルな著名アーティストのウェブサイトは多々あって似た攻撃ができますね。
公式サイトにあるから必ず公式なわけではないhttps://t.co/Hn7dfaS4Fl
作品が重複流通し得ることとは別の角度からの不正の実例として,アーティストや作品の権利運用組織の公式サイトを改竄して,偽物の NFT を売るという事件が,バンクシーの作品で起こりました.
購入者が,「作品の真贋の認証機関の一つであるアーティストの公式サイトで確認した NFT」 は偽物であり,その偽物の NFT は「重複発行されていない唯一なもの」です.つまり唯一性とはそれ単独では無意味で,作品の真正性とは無関係です.
大抵の作品の認証機関にはブロックチェーンほどの堅牢性はなく,攻撃の実現性は高く,現実的です.
この事例や上述してきたことから明らかなように,NFT であれば作品データの唯一性を持つという主張は,正しくないばかりか作品の実運用における重要な要求を隠しています.
実運用で求められるのは「この世界における作品の唯一性と,真贋の確証」であって,NFT はそれを保証せず,贋作は実際に流通し,上述以外にも様々な攻撃方法があります.
そういった不正の実現性とインセンティヴを高めているのはそれぞれ,「ほとんどの NFT が作品のオリジナルデータを誰でも特別な技能無しでコピーできること(ブラウザの拡張機能を入れれば右クリックでデータをコピーできる)」と,「それを希少物として高額で販売していること」でしょう.両条件が揃わないようにできるにもかかわらず,非常に中途半端な技術選定と価値観で動いているの現状の NFT です.
(ちなみに前者の問題は,秘密計算系のチェーンで実用的に閲覧制限できそうですが,自分でコード読んで動かして実用性などを検証しないといけないので判断までしばらくかかります.というか次の章で書いてるように僕のNFTでもそれには対処してましたが,やはり後述する作品寿命の問題が残ります)
ここで書いたような不正は,NFT 特有ではなく他の作品データ販売でも起こります.しかしそれは言い換えれば,「NFT は作品データ販売における問題を解決していない」ということです.(にもかかわらず,それを解決した発明であるかのように喧伝しています.)
少し脱線しますが,不正行為は永久にバレないことが重要なのではなく,犯人が捕まらずに金儲けや攻撃を実行して成功できればいい上に,インターネットや暗号通貨は匿名性を高めて活動することができます.そもそも上述したような唯一性を崩す面倒くさい贋作行為など抜きに,マルウェアでも仕込んで手っ取り早く直接的に攻撃される危険もあります.Bitcoin の利用用途として確立したランサムウェアでも,大金を得るならセキュリティの厳しい企業に挑む必要があるのに対して(個人だと大した金額とれない),アート作品の NFT では数百万とか数千万円の単位を一件の攻撃で得られる上に,それらが束になって一か所にあり,管理しているのが情弱のアート関係者や優秀でないNFTフロントサービス会社(事実,盗難されてる)で,さらに攻撃者はめっちゃ賢いという現実を見ましょう.
NFT にごちゃごちゃと認証機能を加えたところで,鍵を盗られたりシステムや人的関係をハックされれば終わりなわけで,さらに上述した状況に置かれているのが NFT ですから,「唯一性がある,真正性がある」などの妄言を頼りにせずに,まずはリスクのあるものを扱うのだと理解すべきです.NFT企業によるアホみたいな誇大広告を信じてる時点で,NFTがどうこう以前に,ただのカモです.(唯一性や真正性って資産を保護するためのものですよね.実現していないことを嘘をついて客に売り込むのは詐欺まがいの宣伝行為であって,それを信じてる人は既に詐欺に引っかかっているということですから,資産を守る能力はないと自覚した方がいいです.参入したくても,ある程度は信用に足る情報を選別できるようになってからでも遅くはないですから,落ち着いて考えてください.)
アーティスト本人や正規ギャラリーなどが販売しているかどうかの証明を含め,デジタル作品の真贋を確かにする技術はありますが,それは NFT とは別の独立した技術で,NFT ではない他のデジタル作品の販売管理のシステムにも使えます.
そもそも NFT にはアート資産として他の構造的な欠陥や課題があり,アーティストは他の方法も含めて自分に適した選択の自由を持つべきです.
あたかも NFT がデジタル作品の最も優れたソリューションであると印象づけるために繰り返される,「ブロックチェーンを使った NFT だから,デジタル作品の唯一性がある」という主張は,現実のリスクを隠し,他のデジタル作品のシステムの発展を阻む,悪質なデマだと思います.
最後についでに書いておきますが,「NFT は改竄不可能な作品証明書だからデジタル作品を真正を保護できる」というのも,嘘です.上述したように,証明書の真贋は NFT が担当する箇所ではなく,そもそも本物を改竄せずに偽の証明書を流通させられます.
証明書の改竄の有無を判定したいなら,電子署名した証明書データのハッシュを公証しておけばいいだけです.データを改竄したらハッシュは変わるので一目でバレます.
改竄したらバレる作品のデジタル証明書は NFT 以前からあり,NFT が発明したものではありません.その証明書が本人のものであるかの確認には NFT ではない別の技術が必要です.
2.追及権
「ブロックチェーンや NFT によって,これまで実現できなかった,転売時にクリエイターがロイヤルティを得られる追及権が実現された」という主張ですが, 追及権は法制化された著作者の権利であって,NFT では実現されていません.
追及権(ついきゅうけん、英 resale right、仏 droit de suite)は、著作者の権利の一つ。芸術家が、自らの作品が転売されるごとに作品の売価の一部を得ることができる権利を言う。著作者の経済的利益を保証する権利であるため、著作権の支分権として位置づけられるが、他人に譲渡することができない(一身専属性)ため、著作者人格権としての性質をも併有する。
追及権 – Wikipedia
NFT のマーケットプレイスには転売時のロイヤルティが簡単に設定できるものが多いのは事実でいいのですが,一般的な規格の NFT は,Bitcoin などの暗号通貨と同様にウォレット同士で直接送信できたり(AさんからBさんのウォレットに NFT を直接送ると,クリエイターであるCさんへのロイヤルティ支払いは発生しない),マーケットプレイスの外に別でデプロイしたスワップ用のコントラクトを経由することで安全に暗号通貨と交換ができます(ロイヤルティが発生しない売買ができる).
今使われている NFT 自体には,クリエイターへのロイヤルティ支払いの強制力はありません.任意です.こういった迂回の方法は,NFT の一次販売時に継続的なロイヤルティ支払いを別途契約していなければ合法です.
たとえば,OpenSeaの中で NFT を売買しているときにはクリエイターへのロイヤルティは発生させられますが,その外に出して取引すれば発生しません.NFT を別のマーケットプレイスに移行する場合は,そこがロイヤルティ規格に対応していればいいのですが,対応しない場合は(移行手続きをした人が新たに設定しなければ)ロイヤルティは発生しませんから,マーケットプレイス次第で変わることになります.
また,ブロックチェーン外であるオークションハウスで NFT が販売される場合も,ただトークンを発行しただけでロイヤルティ契約を結んでいなければ,オークション側にその支払いの義務はありません(これまで通り,数億で売れても作者には一円も入りません).それを義務化できるのが追及権です.
ですから,「NFT であればクリエイターに永続的にロイヤルティが支払われる」というのは誇張による誤解です.恐らく追及権と結びつけて解釈したので,著作権料徴収のようにずっと支払われる権利が実現されたと思ったのでしょう.
NFT のロイヤルティは,それに対応する特定のマーケットプレイス内で実現する限定的なものです.(NFT はそもそもアート作品専用に考案されたものではないですから,作者へのロイヤルティを強制できるように規格化はされませんでした.よってその実現は各自の実装に委ねられますが,そうすると NFT ではない他のウェブサービスのデータ市場と大差がなくなります)
クリエイターへのロイヤルティ支払いは,別に NFT でなくても電子取引であれば普通に実現できることです.
銀行振込しかない時代なら難しかったことですが,今はクレジットカードや暗号通貨での電子取引が簡単にできて,作品売買のオペレーションのどこかにロイヤルティ支払いを実用的に組み込めます.NFT ではない,ただのデジタルデータの二次流通のマーケットプレイスに StripeやPaypalを使って利益の分配機能を付ければいいだけですし,NFT 以前のデジタルアートのプラットフォームでは,それを使って作品の取引ごとにアーティストにロイヤルティを分配するものがありました.つまり NFT が実現した新しい機能でもありません.
オフライン取引のような,そういったロイヤルティ支払い機能を備えるオンラインサービス外での取引においても,そもそも作品販売の契約書に転売時のロイヤルティ支払いを定めておけば,データの作品ではない絵画などの物品でも転売時の利益還元は実現できます.二次市場での売買時にアーティストへロイヤルティを支払うことを契約しておけばいいだけで,それ専用の支払いゲートウェイを用意するなどの利便性を高めるための方法はいくつもあります.
NFT で販売する場合でも,別途ロイヤルティ支払いを定める契約はしなければなりませんから(しなければ合法的に迂回できるので),結局は契約で法的に縛ることになります.あるいは強制はせずに任意だったり,取引の便利さやアーティスト支援を優先する作品購入者に対しては,普通のウェブサービスとして「二次流通可能な作品データのマーケットプレイス」をつくって,利便性を高めることで人々に選ばれるものを使ってもらえばいいだけです.
実際に NFT 以外の先例があるように,二次市場からの利益還元はブロックチェーン上のトークンであるが故の特権的なものではありません.他のデジタル作品の取引でも普通にできます.
「他のものでもできるが,NFT でもできる」を「NFT だからこそできる」と,いちいち嘘をつくのが問題なのです.
NFT であれば,資産の分割所有や金利が生まれるようにしたり,転売時にクリエイターに対してだけロイヤルティを支払うのではなくて NFT の保有者たちにも分配するような(株の配当のような)複雑な処理ができるという主張もありますが,そうすると有価証券に該当して証券法に違反するリスクが高くなります.最近はSEC(米国証券取引委員会)の規制に備えて,そういった疑いのある NFT が大手のマーケットプレイスからデリストされています.遅かれ早かれ日本でも規制されると思います.(ちなみに,NFTファンドなどを目指した DAO(自律分散組織)をつくれることが優位性であると主張し,DAOではないものをDAOと呼んで脱法を肯定しているだけのプロジェクトが多々ありますが,それらも同様に規制が強化される流れになっています)
3.デジタル所有権
次に,「NFT はデジタル作品の所有権を取引できる」という類のものです.これは非専門の僕が書くのもどうかと思うので,少なくとも日本では「無体物には所有権はそもそも無い.NFT に求められるのは著作物の利用に関するライセンス契約である」ということを法律家が指摘しているはずですから探してみてください.
所有権は、「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利」であると定義されていますが(民法206条)、ここでいう所有権の対象となる所有「物」は、「有体物」であるとされています(同法85条)。
仮想通貨が所有権の対象とならないことは、東京地裁平成27年8月5日判決においても判断されています。
仮想通貨の取引における当事者間の権利関係とトラブルが生じた場合の法的問題点 – BUSINESS LAWYERS
Bitcoin などの暗号通貨に所有権があるのかは昔から問題になっていましたから,これに関しては決着がついているはずです.その延長で,(どの国の人たちかは知りませんが)NFT に関しても何年か前から「トークンのownershipとしか書きようがないけど,作品のlegal ownershipやownership rightではない」という話はしていたと記憶してます.
NFT で取引しているのは作品データではなくてトークンです.ブロックチェーン上のトークンは秘密鍵を持つ人にしか動かせないため,自分だけがそのトークンを持っている状態になります.暗号通貨のコインと違って非代替的なトークンであるとはいえ,その状態は必ずしも自分だけが作品を持っていることと同じではありません.あるいはトークン自体が作品である,という解釈では独占的な保有は確立されますが,そうすると後述のように作品の寿命問題が顕在化します.
“NFTアート”では,作品をどれと見なして何を持っていることにするかを,誤魔化しながら運用しているのが現状でしょう.
また,ただNFTを取引するだけでは,作品を他人に見せるために展示する権利などが渡されるわけではないので,著作物利用のライセンス契約を別途しておかなければ,高額で NFT を購入してもトークン以外は特に何も買ったことにならない(作品をろくに使えない)という状態になるはずです.下記の引用元は今ググって見つけた NFT に特化した記事です.
著作物の利用方法は様々です。「読む」、「観る」、「聴く」といった行為には著作権者の許諾は不要ですが、「複製」、「展示」、「上映」、「公衆送信」(≒インターネット配信)、「翻案」(≒新たな著作物の創作)などの一定の行為については、原則として、著作権者の承諾が必要です。
話題のNFT。権利関係を見てみよう 岡本健太郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts (kottolaw.com)
NFT のライセンス契約に関しては,解決可能な課題なので特に問題視していませんが,トークンが複雑化するほど,後述する寿命問題への対処が困難になります.
結局は普通に著作物のライセンス契約によって,不正利用を技術ではなくて法的に縛るわけですから,NFT にせずに,普通に排他的なデータ供給とライセンス契約のシンプルで便利な取引システムをつくればいいのではないかと思っています.
補足すると,たとえば NFT作品Aの保有者が,「その NFT を保有したまま,その作品データをコピーして別の NFT作品Bを発行して販売すること」は,法律で禁じなければ技術的には簡単にできます.
一方で Bitcoin の場合は,「1BTC の保有者がそれを保有したまま,それをコピーして新たに 1BTC を発行して利用すること」は技術的にできません(十分なブロックの承認があれば現実的でなくなる).法律があろうがなかろうが,それを技術で防ぐことを目指したシステムだからです.
Bitcoin が革新的だったのは,重複利用(二重支払)などのデジタル資産の不正を,法をふくめた人の解釈や信用に依存せずに,技術で防ぐ発明と認識のパラダイムシフトにあります.それは一般的に「ブロックチェーン上のトークン」と宣伝されるものにも求められるはずの重要な性質で,Trustless と言ったりします(その思想に興味があれば本に書いたので読んでみてください).
しかし,現在アート作品で利用されている NFT にはそれがありません.故に技術的に無意味だとか,NFT を使う意味がないと識者から批判されます.(にもかかわらず,「ブロックチェーン上のトークンであるから凄い,問題解決できる」と喧伝してこの実態を隠しているから,NFT 界隈に対して不信感が強いのです.)
このように不正を技術でなくて法律で縛るのであれば,NFT にしなくても,普通に作品データをウェブサイトでダウンロード販売しても同じでしょう,と思います.購入者のみオリジナル解像度のデータを得られるなどの排他利用を低コストで実現できますし.
4.ブロックチェーンだから永続する
最後に,「ブロックチェーンを使うから,作品や取引や来歴が安全で永続する」という類のものですが,まず永続しません.ブロックチェーン自体が衰退や消滅します.そして衰退すると安全性は著しく下がります.このデマが一番悪質です.
NFT の利用では最大手の Ethereum ですら,競合に負けて15年以内に消滅したり使い物にならなくなるシナリオは普通にあり得ます.Bitcoin を除くその他のブロックチェーンの長期生存は厳しく,最近の NFT 特化型のチェーンなどは,むしろ短命になる可能性の方が高いでしょう.
ここでの競合というのは他のブロックチェーンという意味以外に,「ブロックチェーンではない別の新技術の台頭」を含めてです.他にもブロックチェーン金融危機やブラックスワンによる何らかの危機で破綻するかもしれません.
最近は Ethereum の高い手数料やマイニングによる環境破壊の批判を避けるために,取引所の Binance が運営するブロックチェーンの BSC(Binance Smart Chain)や,Ethereum の L2 と自称してるが実態はサイドチェーンみたいな Polygon などの他のチェーンで発行しているアート作品の NFT もありますが,それらの NFT の長期生存はほとんど期待できないと思います.僕から見たら正気じゃないというか,手数料などの運営企業側の都合のみを優先していて,本当に作品を軽視しているのでしょう.(代替チェーンを使う理由は,低い手数料を含めた「ユーザー体験を優先して」と弁明されてますが「使い勝手が悪いとユーザーが離脱して自社ビジネスが失敗することを懸念して」の間違いですよね.優先順位を下げられた作品が切り捨てられているという事実だけを見ましょう)
ブロックチェーンは多くの資金が集まって開発が継続されることでセキュリティが維持される仕組みですから,将来に過疎って資金も抜けて弱体化してしまうと,低コストで攻撃できるようになり,データの改竄でも何でもやって破綻させられます.
ですから,ブロックチェーンが安定して動く期間を甘く見積もり過ぎない方がいいです.もし長期的に安全さを保って生き残れたらラッキーくらいに思ってた方がいい.
ブロックチェーンの利点として「AWSなどのクラウドとは違って改竄されない」的なことを言いますが,それは「現実にはクラウドの一般的な用途ではそんな簡単に改竄も不正もされなくても,敵は存在して事故は起こるものだ」と,できるだけ危機を想定する姿勢として評価されるもののはずです.その姿勢であれば,なんらかの危機でブロックチェーンが安定的に運用できなくなるリスクも当然に想定すべきなのですが,なぜ何の根拠もなく永続するとか長生きするとか思っているのでしょうか.ただのダブルスタンダードですよ.
この寿命の問題でよくある誤解は,「NFT にはデータの永続性がない」というものですが,それに関しては実用的な解はあります.なぜなら,同一性を証明できるデータを将来にアクセスできるようにすれば良く,データは様々な方法と媒体に乗り換えて保存していけるからです.その上で,NFTのコントラクトというかメタデータの設計を変えて,URL ではなくデータのハッシュを書いて真正を検証する,などの対策をとります.問題なのは「NFT の寿命」の方です.
NFT の寿命は,完全にブロックチェーンに依存します.NFT は,上述したライセンス契約やブロックチェーンの機能や記録や堅牢性などの環境が丸ごとあって成立します.NFT を発行したブロックチェーンが消失したら,その NFT も消失し,弱体化したら攻撃されて改竄や破壊されます.NFT にとってブロックチェーンは不可分です.
ブロックチェーンを使う利点でもあるのは,「一蓮托生で,ほとんどの利用者にとっては他力本願」という性質ですが,これは諸刃の剣です.
あるブロックチェーンが人気で資金が集まって上手く行っているときは,個々人は多少の手数料を支払うだけで,堅牢で公的で第三者に改竄されない分散台帳を使うことができます.
しかし上手く行かなくなって資金と人が抜けていくと,NFT の発行時には莫大な金額のステーキングや計算資源で支えられていたセキュリティは維持できなくなり,残った人たちでそれらを再投入することはできず,自分の NFT を守りたいと思っても個人やお金持ち程度ではどうすることもできず,ブロックチェーンが衰退していくことを止められません.
たとえば,あなたがキャンバスに絵を描いて長期間安全に保存したければ,耐火金庫に入れるなり何なりで,個人の頑張り次第で独立してその資産を守ることができます.しかしブロックチェーンは危機に陥ると自分の資産を独立して守る方法はなく,一蓮托生で全てが沈没します.これが Bitcoin などのお金の場合であれば,価値を価格に変換して別のお金に換えればいいだけなのですが,NFT の場合はその NFT が代替できない固有の価値を持つはずですから,そうはなりません.
(ちなみに僕が昔Redditでこのことを指摘したら,Ethereumを推進する誰かに「最悪は自分一人だけでもブロックチェーンを動かせる.分散システムだから寿命はない」という寝言を返されたのですが,一人で動かすブロックチェーンなど安全性はほぼ無くて攻撃し放題です.こういった現実には無意味な理屈で,ブロックチェーンは永続するという類の幻想がつくられています.)
この問題に対して,ブロックチェーンが危機になったら他の何かに乗り換える,ということは解に思えるかもしれませんが,複雑な環境丸ごとで成立したトークンと同等のものを,誰が,いつ,どこに,どうやって,改竄や不正なく移転されられるのでしょうか.
移転システムを作るためには移転先が何であるかが定まらなればなりませんが,いつ危機になるか分からず,その時に何が移転先として適切な世界になっているか,未来のことなど誰にも分かりません.事前に移転システムをつくっても,将来に移転先のシステムがそれを受け入れる保証はありませんし,現時点で正当な移転システムが存在すれば,それを悪用することによる不正複製などの攻撃にも対処が必要になります.
大本であるブロックチェーンが危機的になっている状況において,その上で稼働している NFT ビジネスに余裕があるわけがなく(潰れる間際だったり潰れてたりして),複雑な資産の安全な移転という高コストの作業は期待できないでしょうし,そもそも移転という作業が発生する以上は,移転者である誰かを信用しなければなりません.その時には,NFT 発行時に信用していた人たちはいなくなっているかもしれません.
つまり,根拠がほとんどない状態で「将来に誰かがやってくれるだろう」と思うしかありません.今はブロックチェーンが人気なので,そう期待している人もいるかもしれませんが,将来には新しい技術が台頭し,今動いているようなブロックチェーンには誰も見向きもしない世界になっているかもしれません.
(僕は自作品で NFT を発行したときは,「将来何かあったら責任もって自分で移転しよう」と思ってましたが,僕が早死にしたら終わりですからこれは無責任です.同様に NFT 企業が「将来の移転は自分たちが責任を持ちます」と約束しても,実現できる根拠は何もありません.)
NFT の価値は,トークンとしての価値であって,紐づけられたデータ自体の価値ではありません.
もしトークンではなくデータ自体が価値なのであれば,NFT のデータをコピーしてUSBメモリに入れて同じ価格で売ってもいいはずです. あるアーティストがある時につくった作品のデータであることの証明は,NFT を使わずに,そのデータのタイムスタンプをとって公証することで実現できますから, USBメモリのデータが本物の作品であることは証明できます.
しかし実際にはそれは認められず,NFT として何らかの希少性と独自性を実現することに価値を見出したはずです.なので,その NFT が崩れた時点でおかしなことになります.
たとえば,紙の契約書で作品データを保護したとします.その契約書のインクか紙が十年くらいで崩壊して文字が読めなくなると,未来ではどういった契約だったのか確かめられなくなります.同じ作品データを複数の人たちが持っていて,みんなが自分が現在の正統な所有者だと主張できてしまいます.
契約書というよりも NFT 自体が作品だという認識の場合は,例えるまでもなくシンプルに作品が崩壊するという事です.
そういったものをリスクの説明なしに,あるいは永続すると嘘を言って,それなりの高額で売ることを,アーティストとしてどう思うかです.なんとも思わない人もいるのでしょう.
アートにおける NFT は,NFT として残っていかなければならず,その条件は大変に厳しいです.これは正確にはブロックチェーンの寿命の長さというよりも,独立して資産を守れないブロックチェーンと NFT が不可分であることに起因しています.
他の技術を使えば解決できる問題を,NFT は存在の根幹に抱えているため,アート利用においては競合に負けて衰退していくシナリオが有力だろうと僕は考えています.
(ここでは原理的な問題であると示すためにブロックチェーンの寿命の事だけ書きましたが,実際はそこに乗っかっている各サービスや,使用されている内部のライブラリなどが衰退して,セキュリティインシデント頻発や更新停止や廃棄などとなり実用的でなくなっていく,など他の複雑なことが重なるはずです)
この問題は NFT だけではなく,作品の証明書や来歴のレジストリとしてブロックチェーンとトークンを使う場合も同様です.解決策は今のところありません.(問題としては NFT よりもこちらの方が大きいかもしれません.

*長期間というのをイメージしずらいかもしれないので参考情報です.
この画像は僕が2013年につくった Generative Prints というインクジェット印刷の作品の一つです.専用のインクと紙を使っているので,普通にアクリル額装などして適切に室内で飾ると100年くらい,普通の暗所保存だと200年くらいは退色せずにもちます(保存方法次第でもっと).また,僕は作品の証明書には和紙を使っているので,適切に保管すれば数百年ともつはずです.
インクジェット印刷は,保存性ではアート作品の中での強い部類には入らないでしょう.全部作り方と保管方法次第ですが,油画だと500年以上もってるのもあるし,物質的に安定しているガラス作品などは,もっとずっと長持ちします(作り方次第で半永久的に.
NFT はアート資産としては明らかに短命です.ですから「ブロックチェーンだと永続する」と言う人を見るたびに,「何言ってんだこいつら」と思っています.
5.これらから導かれるもの
他にも色々とありますが,ここでは目立っている四つに絞りました.
2021年でも未だにこういったデマが蔓延している,というよりも,デマばかりが一般的なメディアで支配的に流通していることを見れば,この領域がいかに不誠実であるかが分かると思います.
「問題を明らかにして解決していく」という価値観や姿勢ではありません.嘘を流布し,不都合なことは隠して誤魔化しています.
悪質だと思うのは,「Bitcoinが二重支払い問題を解決した,というような技術の発明」や,それによる「電子的かつ分散的な価値の流通について暗号通貨が獲得した信用」の宣伝効果だけを流用して,「NFT はデジタル作品の売買と流通の問題を解決した革新的なもの」という印象を植え付けるために,あらゆる嘘を塗り重ねていることです.
デジタル貨幣に BitcoinのProof of work が必要だったように,デジタル作品にも何か画期的な発明が必要です.しかしそれは NFT にはありません.(現実には銀の弾丸は無く,問題を抱え続けることになるのでしょうが,僕はそれらしいものをずっと探しています.)
ここで指摘したことは,暗号通貨とアートの知識があるなら普通に分かることです.ですから,当該のデマを言っている人がいたら下記のどちらかなので十分に気をつけた方がいいでしょう.
- この程度のことすら分かっていなかったのであれば,有識者ではなく,他人のアート作品を扱ってビジネスをする能力も資格もありません.
- あるいは,問題を分かっているのに嘘をついていたのであれば,詐欺師です.他人を騙す意思があります.1よりもヤバい.
ここで指摘したことだけピンポイントで分かってなかったなどは有り得ないので,他の事でも同様に信用できないと思った方がいいでしょう.しかし残念ながら NFT とアートで表の言説をつくっているのは,そういった人たちではないでしょうか.(実際にメディアに出てる自称有識者がとんでもない事を言ってますよね.
自由を求めて
僕は19年に作品「SUPER GREEN」の NFTコントラクトを自分で書いてデプロイしました.Ethereum の EIP-721 規格をベースにしたカスタムコントラクトで,作品画像データがプレビューのみ公開されて高解像度データは購入者のみが得られる仕組みや,二次販売で利益の一部を作家が得られる追及権的な代理コントラクト,堅牢性を犠牲にして自分の死後の管理権限の譲渡を可能にしたりコントラクトをアップグレーダブルにしたりなど,当時に思いついたほとんどの必要そうなことを実装していました.以下に補足するように,実用に必要な機能を実装すると,ブロックチェーン上のトークンとしての独立性と Trustlessさを失います.今となっては,NFT ならデジタル作品の流通に使える開発環境が整備されているという恩恵はあっても,長期的に見れば依存関係が複雑化するので, NFT ではない別の方法でデータ販売してもいいのではと思います.
(一部の気になる人向けの補足ですが,高解像度データの閲覧制限は,外部サーバーでNFT保有者の鍵を検証してデータを渡してるだけです.
また当時は NFT 単体の内部で転売時のロイヤルティ支払いを定める規格はなく,内部にその機能を書くと OpenSeaなどの各プラットフォーム側のシステムと衝突するか何かで書けなかったと記憶しています.なので実用のために,NFT を出品する各プラットフォーム上ではそこの機能を使い,その外部では NFT 運用を代理させるために作った別のコントラクトを間に噛ませて取引を中継することで対応していました.今は EIP-2981 としてプラットフォーム間を跨ぐロイヤルティが規格化されたそうで,まだ仕様を読んでないですがそういったものを使えばいいのでしょう.ただ規格化されても結局は他のプラットフォームが受け入れないと使えないので,その点は注意です.
また文末の堅牢性を犠牲にした機能は,美術品の実務上必要だったり,Ehtereumの古いチェーン上の資産の扱いが将来どうなるか不明だったりで対応せざるを得なかったものです.)
つくった NFT はハイブリッド・エディションという複数メディアで構成される作品形式の一つとして,OpenSea で売りに出しましたが,やはり倫理的に問題を許容できないのでしばらくして販売を取り下げました.
その NFT は今でも OpenSea にありますが,コントラクトは独立しているので,そこから引き揚げて同じ規格に対応する別のマーケットプレイスに出品したり,どこにも出さずに放棄することもできます.
僕は自由であることを重視するので,できるだけそう扱えるように作りました.しかし実現できたのは Ethereumのマケプレ間を移動できるとか,その程度の事でしかありません.NFT がアーティストにもたらすものは何なのでしょうか.
NFT の利点は,それ単体よりも標準規格化が可能にする周辺サービスを含めたエコシステムの発展性にあると思います.不特定多数の人がそれぞれでサービスをつくる場合に,規格を共通にすると相互運用性を得られ,関連する他のサービスも連鎖的につくられて全体的な発展が加速します.
NFT単体の売買機能だけでは実社会での要請に対して不十分なので,アーティストの本人確認をしたり,複雑な権利移転ができるようにしたり,アート作品を運用するための実用的なサービスが必要となります.それが便利で不可欠になるほど,アーティストは強く拘束されることになりますから,特定のサービスにロックインされないかに気を使います.アーティスト活動の生殺与奪の権利を,特定企業に委ねてしまうことになりかねないからです.(極論的に例えると,楽曲の権利運用をしなければ食べていけず,かつ JASRAC しか権利運用組織が運営できない世界の場合は,音楽家はJASRACの意向に従わざるを得ません.JASRACが初めの頃は親切で手数料が安かったりしても,権力を強めたり代表者が変わったりして,不親切で搾取する組織になるかもしれません.ロックインにはそういった怖さがあります)
NFT が初期の頃は,表ではオープンソースソフトウェア開発のような開かれた文化を装っていて,その懸念を払拭できることが大きな魅力でした.しかし数年経ってみて,裏では普通に様々な実用的なサービス用の特許がとられていたと分かり(当然今も特許競争が行われている),そういった文化圏のものであることが明らかになりました.
特許にはシステムの設計を変えることでの迂回方法があるとはいえ,「ブロックチェーンと NFT をアート作品で使う」という条件では,効率的な仕組みは相当に制限されるはずで,既に手垢がついた不自由な領域に見えます.誰が見ても分かる顕著な結果が表れるのは,もう数年先でしょう.
結局は,これまでの他のものと変わらない普通のビジネスで,支配と独占の論理で動いています.自由だと期待していたものは思ったほど自由ではなく,アーティストとしてその発展にわざわざ加担すべきなのかは疑問です.
NFT を使わずに普通に独立して作品データを販売した方がいいのでは?(それがダメな理由が今のところ思いつかないです.)
ちなみに期待されるエコシステムの実態の話ではなく,NFT単体の規格の話でも誤解している人が多いので補足しますが,規格準拠の NFT だとしても,そのコントラクトの独立具合や運用の発展性は作り方次第で変わります.中には,手数料を下げるために一つの共用コントラクトに全てのクリエイターの作品をまとめて入れているものや,発行したプラットフォームに事実上は縛られるものもあり,それらも一律に NFT と呼ばれていますから,コントラクトを自分で確認しないと資産としての堅牢性や自由度などを誤解したまま自作品を発行してしまう事になりかねません.
最低限の NFT単体の自由と発展性すら確保できていないというコントラクトの実態を,利用者に説明していないことがあるので注意が必要です. とにかく人とカネを集めるために作られた宣伝用の印象と,実態が違い過ぎることが多いです.
(ちなみにこれはパブリックブロックチェーンを使ってる場合の話で,コンソーシアムとかプライベートチェーンとか使っているものは,そもそも論外です)
◆自由なデータ,自由な世界
資産寿命や分散性や実用性や運用時の税制など,自分で作ることで考えられるようになったことは多々あった中で,最も印象が強かったのは「こんなことに一体何の意味があるのか」という疑問でした.
元記事にも書きましたが「そもそもデジタルデータを希少品として排他的に扱うこと自体」が賢くないというか,これまで通りの物品を扱うための古い価値観です.
デジタルデータの無劣化の複製可能さや,配布の自由さ,所有という概念の転換などの新しさを捨てて,古い価値観を共有する人たちと金融システムから受け入れられるからこそ,NFTは多くの人に基本的な概念を理解されたり投機目的とはいえ購入されてコレクションされるようになっています.
“NFT アート”とは,新しい技術でつくられた古い価値観の作品形式です.アート表現における革新的な技術の扱い方ではなくて,極めて凡庸なデジタルプロダクトです.そこに概念や感性の更新はほとんどありません.“NFT アート”を新しいアートと呼ぶことは間違っています.(後章で書きますが,新しいと言われているものは過去に既にあったものばかりです)
僕はアートにおける NFT を,作品の「挑戦なき市場化」に分類しています. あまり新しさがないということは,大きなコストや痛みもなく,アーティストはデジタル作品を販売して収益を得られます.理想とは別に,アーティストは今,制作費などを必要としています.
インターネットの普及で実現した,各自が独立してつくるウェブサイトでの自由な作品データの販売などを,唯一性や相互運用性の無さなどを理由に不正が横行する前時代的なものと位置づけて,その問題を解決していない NFT という「特定のブロックチェーンネットワークやマーケットプレイスにアーティストと作品を強依存させる不自由な拘束」を「インターネットの次の段階である Web3.0」などと呼ぶような欺瞞が明らかであっても,Web2.0 の Apple や Google のプラットフォームを使うのと同じく,便利で儲かるならいいかと割り切って考えることにしました.
NFTビジネスの受益者たちに都合よくチェリーピッキングして利用されないように回りくどく書きましたが,これは現時点では利点だと思います.
一方で,そういった利点にも見えない穴があります.NFT はアートとして新しくないだけであって,暗号資産という新しい仕組みを使っているが故のリスクはアーティストも引き受けなければなりません.ポール・ヴィリリオのいうように技術は新しい事故を発明するものであり,未知のリスクを必然的に抱えるという視点です.
一般的な crypto assets の意味でなく,日本の法律用語の「暗号資産(前は仮想通貨だった)」に該当しない作品利用の NFT にはリスクがないと言う人もいますが,技術とは何であるかの根本的なことが理解できていないのでしょう.
単にデジタル作品を売るだけにもかかわらず,アーティストにとっては不必要な足枷を付け加えただけなのではないかという懸念があります.新しくないことの価値を享受できないのではないか,ということです.(リスクについては後章に書きます.またこれはまともな産業にする場合の話で,バブル期に先行参入して売り逃げとかは論外です)
NFTビジネスの受益者たちが喧伝する「NFT がアーティストに自由をもたらす」というような主張は,極めて危うい間違いだと思います.実際は「データを希少にする」という価値観に従っているために,これまで通りのごく普通の資本主義の仕組みにデジタルアートも飲み込まれてしまっただけです.(データを希少にしないオープンエディションなら NFT にする意味は全くないです)
期待してどれだけ自分で仕組みを理解してハックしても,行き着く先は新たな支配への気づきです.変わらない世界で,これまでと同じような割り切りを求められます.
デジタルメディアによるアート,という意味を内包する宿命にあるデジタルアートという概念は,そういうものとして既成事実化されてしまうことになるのでしょう.僕はまた敗北したのだと思う.
今のようなデジタルメディアのアート市場の遅れた開拓期に,NFT が標準として整備されてしまうと,それが既得権益化して将来に必要な変化が起こせなくなるのだろうと思います.たとえ欠陥を抱えていたり非効率的であっても,それを使い続けて手放さないだろう,ということです.
アートの世界は広く多様ですが,マクロに見れば時代ごとにリソースが割かれるものに偏りがあり,それが長期間,固定化する傾向にあります.たとえば,近代以降のギャラリーやオークションハウスなどの価格形成の体制は,大きな資金とそれによる権威的な評価を近現代アートに投入することを可能にはしましたが,作品を商品化しなかった Media Art などの他の同時代的な領域はそこからはじかれたまま,領域ごとに格差と分断ができる歪な世界が長く続きました.(Media Art は広告業界など他の制作業務と結びついたためアートの評価を離れたものもあります.他領域もですが一概に言えるものではありません)
資本主義の中において商品化して流通できることは強い力に繋がり,その影響は市場に収まらずに,アーティストの社会的評価や活動領域の制限(棲み分け)などを半ば強要するような理不尽を形成したのだと理解しています.僕自身が以前はそれに強い不満をもっていました.
惰性で続いた体制も時代の大きな要請には勝てずに,今日では一般的な美術館でさえ領域を問わずに展示できるようになっているとはいえ,十数年前まではそうではなかったと記憶しています.
「デジタルアート市場 = NFT」 という既成事実化は,かつての市場体制による理不尽を別の形で再生産する流れに繋がるのではないかと危惧しています.
アートを変えた時代の要請というのは外圧の一種であり,今 NFT 利用を押し込まれつつあるのもデジタル化という外圧によるものだと思います.
誰もが認めるように,アートは音楽や漫画などの他の分野に比べて,主な商業でのデジタル化への対応が異常に遅かったです.アートは特殊な権威性により,変わるべきものが変わらないことが他の分野よりも長く続く傾向にあるのですが,たとえば NFT 利用が目立たない音楽との違いは,デジタル化の対応状況にあるかもしれません.
音楽は先進的に産業に技術を取り込んできたので,既に NFT を必要としない段階になっているだけかもしれず,アートは視覚表現だから NFT に向いているのではなくて,単に外圧に耐えられないくらいに限界までデジタル化に対応していなかったから,今押し込まれつつあるのではないかと考えています.
大きな時代のサイクルの中で,たまたま限界まで弱っていた時期に,NFT がバズって圧力をかけてきたからそれに従う,という構図を仮定します.そうすると,反省すべき過剰な保守性の原因と対策が正面から議論されることがないまま,外圧でただ変わるだけであり,次も別の理不尽の固定化を長期化させ,それが限界になってまた別の外圧で変わる,ということを繰り返すのではないでしょうか.
やはり内省がないとロクな結果にならないと思うので,NFT 以前に,アートでデジタルメディアを扱うという基本的なことを真摯に議論したり試行錯誤すべきです.NFT企業とではなくてアーティストと,です.
近いうちに実用的になるであろう新しいデジタルメディアの資源運用システムが台頭してきても,それへの移行に対応せずに NFT を使い続ける蓋然性が高いと思います.常識的に考えれば,今使えるものは今使い,その問題を乗り越える新しいものが出てきたらそれを使う,と代謝していけばいいはずですが,残念ながら歴史を見る限り他の分野と違ってアートでそれは難しいと思います.
この話は,僕の中でも整理できていないのですが,何か大きな文明のボタンを掛け違えているような気がしてならないのです.(上手く論立てられないのですが,この動きは何かがおかしいんですよ)
もしかすると,アートは現代で唯一残されていた自由なデジタル世界というユートピアを, ”NFT アート”のバブルと流行によって短期的には失ってしまったのかもしれません.
僕が今確信していることは,この問題に比べれば,NFT の資産性や法律などの問題はとても些細なものだということです.
何の話を誰がしているのか
Non-Fungible Tokenとはあくまでコンセプトであって,それを実現する技術も用途も多岐にわたります.
NFT といっても,どの領域でどう使うかによって見方は変わりますから,「NFT の是非」というような漠然とした問い方をしてもあまり意味はありません.
僕が指摘している問題はアート作品に対してであって,チケットやトレーディングカードやファンアート等の他の用途には当てはまるかは分かりません.
たとえば,一般的な使い捨てのチケットのシステムを NFT で作った場合はそれが長寿である必要はないですし,NFTコンテンツのデータとトークンの結びつきが URL のみで十分な用途は多々あります.ミームやポップスターたちの NFT が高額で買われる根拠と効用はアートと同じではありませんし,ゲームやトレカで楽しむことを目的とした NFT に対してアート史における価値の有無は問題となりません.
様々な領域に通じる一般的な技術の問題もあれば,それぞれの領域ごとに異なる専門性が求められることもあります.
”NFT アート”については,何の話を誰がしているのかが整理されておらず,混乱しています.そうなる理由は大きく分けて,話の対象をごちゃ混ぜにしていることと,誰が主体であるかの評価を誤っているからだと思います.
何の話か
まず,話の対象を意図的に混同しています.
主に NFT企業が,アートの NFT の話をしなければならない場面で,その市場規模を水増しするために,明らかにアートではない Profile Picture NFT(アバターNFT)などの取引量のほとんどを占める NFTプロジェクトまでを数字に混入させています.企業は,より多くの投資や業界からの注目を集めるために,NFT ができるだけ高く多く取引され,広く支持されている領域であると印象づけたがります.
また,直接は関係しないはずの他分野の成果や NFT対応状況を援用して「NFT はこれだけ利用されていて,この流れに乗り遅れると損をする」という印象を作り出すために混同は利用されます.他分野のそれがアートでの NFT の実利用の観点では無意味なものであってもです.NFT には用途ごとに向き不向きがあって,重要なのはアートに適しているかどうかのはずです.しかし目的が,実態がどうであれ自社ビジネスの価値が高いように見せることであれば,正確に話をする必要はありません.
アート以外の NFT受益者たちの場合は,特に高額な NFT の無価値さを指摘された時に「価値は絶対的なものでない.アートと同じで分かる人には分かる.」という類いの逃げ口上に利用することが多いです.仮想通貨バブル期の Shit Coins(無価値な糞コイン)の場合は,無価値な詐欺まがいの投機であることを論理的に追求しやすかったのですが,NFT では価値の根拠をアートと類似するものであると言ってしまえば最終的には追及を逃れられる,という思惑が背後にあります.これは NFT がアートを利用した最も悪質なものの一つであり,同時にアートの価値形成の欺瞞を脆弱性として利用された例でもあります.
あとは,NFT にはコミュニティへの参加料も含まれるとか他のユーティリティがあるとか,「この NFT はアートだけでない」などと言ってアート側からの批判をかわし,実際に価格に見合うユーティリティなどではないと批判されると,今度は「これはアートでもある」と言って逃げます.初めからユーティリティの価値で売ればいいはずですが,それだと価格を吊り上げられないのでアートを混ぜて誤魔化します.
要するにこの混同は,「価値と実態の齟齬への糾弾を逃れるためのダブルスタンダードに使われている」ということです.
「NFT は表現物の販売であり,価値の根拠はアートと同じ」というスキームは,詐欺への糾弾を逃れるために実用化されているようです.
このツイートは正確ではなくて,実際は作品として「画像ではなくてトークンを買った」のですが,作品に客観的な価格の指標はありませんから,それを受け取った時点で取引は正しく完了したことになると思います.その作品に対しての価格がアート業界的にも一般的にも非常識であり,明らかに購入は NFT の背後にあるユーティリティや将来的なサービス展開などへの期待によるものであったとしても,詐欺には問えないようです.投資の勧誘にあたる証拠があれば追及できるのでしょうが,記録を残さずに上手く誤魔化す方法もあるのでしょう(この件がどうかは分かりませんが.
NFT とアートを混ぜれば脱法 ICO を実現できるというのは,面白い発見でした.
次に,アートという言葉の難しさによる混乱です.
アートは広い領域で,かつ歴史的な経緯上,言葉の定義が困難になっています.「アートとは何であるか」という定義を更新して領域の拡大や深化を行ってきたのがアートです.デュシャンの「泉」という便器にサインを書いた作品は,有名なのでみんな知ってると思います.「これはアートではない」などとは簡単に言えない事情があります.アートは,そもそもの概念として人間にとって根源的なものですし,あらゆる表現領域を指せますし,誰でも自由に解釈して普通に使える言葉ですから,「使う際に文脈を指定しない」というだけで,何にでも便利に適用できます.しかし,権威的な特定文化圏の価値形成を匂わせるなどの一定の実効的な含みを持たせられます.
そんな「何でもアートと言えてしまう(ように思える)」状況につけ込めば,アートという言葉は効果的に乱用できます.当然それに対して批判はできるのですが,なぜアートでないかと論じることにはそれなりの負担がかかり,かつ多くの場合はそうしても何かが得られるわけではありません.これもフェイクニュースとファクトチェックの非対称性の問題と似ています.いい加減にデマを流す側には楽で儲かるという乱用の利があります.
僕のこの記事では,適切な言葉が浮かばないので単にアートと書いています.正直なところ,自分がイメージしているものをどう一般的に伝えればいいのか分かりません.
一応僕がイメージしているのは,自分の活動領域である現代アートとMedia Artの両領域と,それらを形成するに至った歴史の領域,という感じです.つまり全てのアートを指していません.
誰がしているのか
NFT についての話や企画などの主体の評価を改めた方がいいでしょう.
たとえば今,アートとNFTについての情報を調べても,メディアに出ている情報は自称有識者によるデタラメが多いです.(暗号資産が関わる場合は残念ながら本物の詐欺師も普通に混ざってきます.詐欺師がテレビに有識者として出てたりします).
要するに人選ミスが問題ですが,そもそも必要な知見のある人が少ないので,簡単に解決はできないのかもしれません.
たとえば自作品を NFT にするか否かや,NFT 企画の売り込みを受けて自組織でどう対応するかなど,NFT が何らかの仕事に関わってくる場合は,信用できる複数の情報源や,相手の思惑が何であるかの理解が必要になります.
ここでは状況整理もかねて,僕の見解を書きます.
土台となる基本的な情報が最も重要です.それが間違っていれば,その上で行われる議論も無意味になります.たとえば「NFTは作品の唯一性を保証する」という前提では,それを元に各自で何を考えても無駄です.
自分でそういった仕組みなどの理解をしていくのではなくて,他人の情報を当てにするなら,誰が信用できるかの判別方法を自分なりに明確にしておくといいと思います.その上で,NFTについてではなくて,その判別方法について他者と意見交換をしてみてください.
簡単な判別方法は,この記事の公開前にアートと NFT 関係のメディア記録がある場合はそれを見て,前章の誇大広告のどれかを言っているかを確認します.もし言っていたら絶対に有識者ではありません.立場や肩書が何であってもです.
こういった記事の公開後には,出典も載せずにパクるだけの人が毎度出てややこしいですが,下記の順に条件判定して信用具合をレベル分けするといいと思います.
まずは基本的な能力を測ります.
アートでの問題が分かるのは,アートで仕事をしていてその領域の実情や特性を自分で理解しているからです.たとえば,僕はアイドルに関する知見はないのでその NFT の問題は分かりません.
その上で,アートと NFT であれば,求められるのは単一領域ではなく異なる領域を横断する知見です.たとえば,アートの商習慣を知らない法律家に作品売買についての実地的な見解を求めるのは無理があります.同様に,アート業界で仕事をしていても,暗号通貨の技術も歴史も背後のカラクリも知らない人が NFT とアートを論じても,信用できる専門知にはなりません.
当然の事だと思うでしょうが,これらの前提を満たせているものの方が少ないはずです.試しにメディアでの書き手を調べてみてください.
誤解しないでほしいのは,どのような能力の水準でも論じることは自由であるし,それぞれの価値はあるのですが,そのことと土台としての信用できる情報を提供できるかどうかは別の話だということです.
それらを最低限の条件として,知見から現実の問題を発見する能力があることが求められます.ここで初めて実用的な整理や議論ができるようになるのだと思います.
その能力のある人は少ないでしょうが,探せばいるはずです.(何の根拠もない個人的な肌感覚ですが,各国に数人はいるのではないでしょうか.
次に,立場から思惑を測ります.
NFT に批判的な立場で,金銭的に得をするのは,NFT ではない他のデジタルアートのプラットフォーマーくらいでしょう.ほとんどいない上に情報発信もしていないので,気にしなくていいと思います.損得が関係ない好き嫌いによる立場については除外します.
NFT を推進する立場で,NFT やブロックチェーンのビジネスの受益者たちには必ずそのバイアスがかかっています.そのため夢を多く語り,クリティカルな問題の指摘を避けます.
NFT企業といっても一律ではなく,特に VC から多額のリスクマネーを入れてファンドの期限内に M&A なり IPO なりが求められるスタートアップ企業の場合は,事業を短期間で急拡大させ,ユーザーを大量に囲い込み,他の競合企業に勝つことを指針としていることを踏まえましょう.深刻な問題が発覚しても,ビジネスをピボットしたり畳む必要が出てくるかもしれませんから,場合によってはそれを軽視したり無かったことにしたりします.(美術関係の人はこの手のことに疎すぎます.色々と濃縮されているセラノス事件を調べてみてください.)
そういった状況に置かれている企業が NFT をアート関係者に推すのは,NFT がアートに向いているからでも,アートとして NFT を議論すべき必然性があるからでもなく,その企業が NFT事業で成功しなければならないからです.NFT市場が最低限は整ってからではなく,いま参入を要求してくるのも,先行者利益を得て競合に勝ちたい企業側の都合であって,アーティストの都合ではありません.(アーティストにはもう先行者利益はないです)
他にも金銭とは違う損得として,アートの場合は,自分の友人やコミュニティがやっているから肯定あるいは否定するという縁故主義的な立場をとる傾向も強いと思います.全部が全部ではないですが,「アートは村社会」という揶揄をどこかで聞いたことがあるでしょう.発信者が大学研究者なりキュレーターなり,それらしい肩書の人でも,芸術と知性に対する誠実さが皆無なことはあります.(縁故ではなくてカネ貰ってるのかもしれませんが.
やはり重要なのは金銭の関係だと思います.事業者,スポンサー,提携関係などお金の繋がりを追って立場を理解するのが基本でしょう.
さらに,この見方を応用してみます.
たとえば各国で行われている“NFTアート”の展覧会や企画イベントやオークションなどは,背後で NFT企業が主導しています.アーティストたちが主体的につくっている動向に目立っているものはないはずです.
こういったことの過去の類例だと,タバコ企業によるマーケティングが分かりやすいでしょう.
「タバコを吸うことは格好いい.タバコは束縛からの自由の象徴」といった印象は,ハリウッド映画などへ,タバコ企業がイメージ戦略として多額の支援をすることでつくられたものだと明らかになっています.俳優がいい感じに吸っているタバコが「映画に欠かせない小道具」になったのは,タバコ企業がスポンサーになってそうさせていたからです.クレジットには協力とか提携と書かれて,その影響力が前面には出ないので騙される人が多かったのでしょう.
ちなみに「女性の解放としてのタバコ」もマーケティングによるものだったそうです.(タバコのマーケについては昔まとまった文献を読んだのですが,どれか思い出せなくて,雑なリンク貼りで申し訳ないです.)
最近のアートセンターでの NFT展や,特定のアーティストに注目した NFT企画などは,NFT企業の主催や営業によりつくられています.裏で糸を引いているのは誰かを調べてみてください.
NFT をアート史に位置づける動きというのは,アーティストの要請に応じて生まれたものではありません.
そういった NFT企画に加担してるアーティストやアートセンターなどは,タバコの事例における俳優やスタジオと,そのまま同じことをしているのではないでしょうか.(NFT がタバコのように害であるとかではなくて,企業案件だという話です.事実上の主宰者を誤魔化しているなら,ステルスマーケティングみたいなものですよね.)
“NFT アート”は既に,ブロックチェーンネットワークへの奉仕ですらなく,「NFT企業のマーケティングによる NFT企業のためのアート」だと思います.
アーティスト個々人たちが楽しんでやってる場もあるのですが,領域的には完全に乗っ取られたように見えます.
最後に僕についてですが,独立した個人のアーティストで,基本的に暗号通貨や分散台帳の利用の推進派であり,デジタルメディアの自作品の市場を開拓したいと思っています.その手段の一つとして,今の主流の作品用途とは違う限定的な用途での NFT は受け入れ得るという立場です.(用途の具体例は別の機会に紹介します.)
NFT に期待していた数年前とは違い,現状には大きく失望しており,NFT ではない他の方法で自分の作品を販売した方がいいし,それが標準的になった方がいいと今は思っています.
このように発信者には傾向と思惑がありますから,それらを踏まえて各自で考えてみてください.
ただし一番良いのは,自分で理解して確かめることです.Don’t Trust, Verify.
*予想外に,広い領域のクリエイターさんに読んでいただいているようでありがたいです.誤解があるといけないので,次は使える用途について書きます.上述した誇大広告を垂れ流してる美術界隈のデマ屋や詐欺師たちと距離をとって使うことはできると思います.しかし技術的な観点から作品には不向きといえます(「使うことはできる」という箇所だけ抜き取って都合よく利用されるのでこの点は注意してください).
僕はクリエイターのデジタル制作物の収益化の手段はあった方がいいという考えです.僕自身が10年以上ずっとデータ主体の作品をつくっています.
記事の後半は今は目次だけで,中身は後日に公開します.後半の目次の下に元記事があります.今書いてる感じだと後半の量は上記の前半よりも多いです.追記というレベルではなくなってしまいました.
公開したら Twitterで告知しますから,ぜひフォローしてください
2023年に追記:続きの公開はいつかと聞かれるのですが,公開したくないので公開していません.後半も前半公開後にほぼ出来てて様子見てたら出典も載せずにパクって有識者として活動してる人が結構いたので,それなら自分たちで何とかしてくださいという感じです.核心的なリスクと用途に対する欠陥については前半には書いていませんし,それは未だに一般には知られてませんから,まあ頑張ってください.正直NFTとかどうでもいいです.
後半の目次
適している用途は何か
“NFT アート”について
”NFT アート”への見解を簡単に書きます.これは,そもそも独立した新規表現のカテゴリーとして見るべきものだと思わないので,引用符で囲っていることをご理解ください.
市場化,価格,価値
アート表現としての NFT
表現として評価する前に
本当のリスク
今発行すべきか
NFT よりも前にあったもの
「アート & NFT & ブロックチェーン」の欺瞞
蓄積と検証は意図的に排除されている
なぜ建設的な議論ができないのか
虚構が続く本当の理由
デジタルメディアのアート市場の可能性と実現にむけて
最後に
2ここから下が 2019年の元記事です
*更新 ― 現在はこの販売を中止しています.(販売用の)アート作品としてのNFTの構造上の欠陥を職業倫理的に許容できないからです.
Art&Technologyの分野で活動するアーティストの Goh は,新しいハイブリッド・エディションの作品「SUPER GREEN」をリリースしました.

SUPER GREEN は,枯れることが許されない「Ever Ever Green」であり,物理的な世界にある本物の植物を3Dスキャンして作成したデジタルデータです.
ハイブリッド エディションとは,一つのデータを異なるフォーマット/メディアで出力する新しいアートのフォーマットです.
本作品の場合は,デジタル エディションとフィジカル エディションで構成されています.
- Archive(
デジタル エディションを購入する – at https://opensea.io/collection/goh-digita-art フィジカル エディションを購入する –at https://goh.works/shop/super-green-1/
Digital Edition
– これは4KのJPEGデータで,その所有証は Ethereum Blockchain上での標準規格のERC721に基づいたNFTとしてトークン化されています.
– 限定エディション数は ‘2’ です.
このデジタル資産は このオンライン市場(Archive)で購入して,暗号通貨と同じように自分のウォレットでコレクションできます.
Physical Edition
– ミュージアムグレードの素材を使用した A0 サイズのプリントです.
– 限定エディション数は ‘2’ で,APが ‘1’ です.
これは美術館やギャラリーなどでよく見られる伝統的な作品フォーマットです.このオンラインショップで簡単に購入できます。
2023年追記 – アーカイブへのリンクを貼りました↑。Openseaのページの仕様が変わっており↓で、今後メンテナンスをしたくないためです。
アートの NFT について
印刷作品については皆さんご存知だと思うので,NFT について簡単に説明します.
NFT,「Non-Fungible Token」とは,ブロックチェーン上で発行される資産の一種です.今回はEthereumのブロックチェーンを使っています.
トークンは,コインのより抽象的な概念で,ロイヤリティ ポイントやチケット,証券,所有証など,様々なものを表すことができます.また暗号通貨のコインと同様に,スマートフォンやブラウザ,専用端末の暗号通貨ウォレットで管理することができます。(例:Trustwallet, Metamask, Trezorなどのハードウェア ウォレット).
本作品の場合,我々は NFT の所有者をデジタル アート作品の所有者とみなして,その一つのエディションの所有証を1つのトークンに結びつけます.
「デジタルアート コレクティブル」のシステムは,NFT の取引,高解像度の画像データなどのアート作品データの配布,それらを収集・閲覧・管理するシステムなどの,複数の仕組みを組み合わせて構築されています.
アートにおけるNFTの利点は,作品の所有証とそのアクセスキー(というよりECDSA等の認証のエコシステム)をブロックチェーンで管理することで,エディション番号や来歴をパブリックに確認でき,見知らぬ人とオンラインで簡単かつ公正に取引できることです.
NFTの管理はとても簡単です.Bitcoinを扱うように,安全に保管したり友人に送ることができます.またウェブ上でのセカンダリー マーケットのサービスもすでに提供されているので,自分が持っている NFT を誰かに自由に売ることもできます.
パブリック ブロックチェーン上の標準規格に基づく NFT は,従来のデジタルアートのプラットフォームの深刻な問題であるベンダー ロックインを軽減し,プラットフォームの運営会社が倒産しても自分で資産を管理する自由を実現できます.


しかし,ブロックチェーン上のアート資産の寿命や持続的な供給には,重大な懸念があります.
まず,そのデジタル資産は Ethereum(以外のものであっても,ブロックチェーン自体) の寿命と実用性に依存しています.Ethereum にはスケーラビリティなどの構造的な問題があり,ETH2.0のようなソリューションが成功するかどうかはまだ未知数です.
次に,一般的なNFT規格では,作品そのもののデータやそのメタデータは,ブロックチェーンに書き込まれません.データはブロックチェーンではない他のサーバーにアップロードされ,そのURLのみがトークンに書かれています.(メタデータはDataUrlsでコントラクトに書けますが実装次第です)
つまりデータの改ざんは容易であり,また正しく持続的に供給するためには,NFTの発行者がコンピュータを稼働させ続けるか,サーバー費用を払い続けなければなりません.現状では,分散型ウェブストレージを含めても,データを永遠に供給できるシステムはありません.
(追記:「データを永続的に保管できる」という嘘の誇大広告による誤解が多そうな箇所なので,改めて注意喚起を本文内に書きます.
分散型ストレージには,IPFSや,独自ブロックチェーンでのコイン発行の収益化で維持費を捻出する前払い無期限契約でデータを保管するもの,ブロックチェーン自体にコンテンツのデータを格納するものなど,いろいろ(当時から)ありますが,永続するものはありません.まずブロックチェーン自体が現実的には永続しません.むしろ短命なものの方が多いです.
現代の技術では必ず誰かが,データの供給を維持しなければならずトラブルの際には対処しなければならないことを忘れないでください.
それを踏まえた上で僕はIPFS を使っていました.(ただし同技術を使っていても,耐改竄性や長期的な一貫性などの実態は異なることがあるので注意が必要です.実用のためにコントラクトを更新可能にしていることは多々あり,実装次第では後から作品データの参照を変更できるようにすることも可能でしょう.メタデータのファイルをIPFSに置いても,その内の作品コンテンツの参照がデータの同一を保証しない普通のサーバのURLなどであれば,データは改竄できます.またメタデータをDataUrlsで直書きして作品をIPFSに置いても,結局はコントラクトから読みだすのはURLなので,https://ipfs.ioなどのドメインが失効すると大抵の人は元の作品データを参照できず,ドメインが乗っ取られた場合は別の作品データへと改竄される可能性もあります.)
また,実際の運用では,管理者権限の機能が NFT のコントラクトに実装されています(コントラクトとは,ブロックチェーン上で動作するNFTを発行するコンピュータ プログラムのことです). 実装によって権限は異なりますが,コントラクトの管理者の秘密鍵が盗まれたり,管理者が悪意を持っていたりすると,不正な NFT の発行や焼失,送金阻止など様々な攻撃が発生する可能性があります.
当然ながら,NFT の発行者が,そのコントラクトやブロックチェーンのシステムの外で作品を不正に販売することも可能です.
そのため,コレクターは NFT の発行者を信頼する必要があります.正確に言うと,主にコントラクトの管理者です.
(追記:そのまま訳しましたが,語弊のある書き方だったので説明します.
上記の「主にコントラクトの管理者」というのは,「NFT コントラクトの不正運用」などに対しての主体です.上述した追記のように,コントラクトは実装次第でいろいろなことができます.最小構成のNFT規格は使い勝手が悪いので,コントラクトを改良していることは多く,改良コントラクトや普通のサーバーと連動させた便利な運用方法などは,できることが増える分だけ悪用も可能になります.利用者が安全性を判断するといっても,設計を理解した上で関連するコントラクトを全て自分で確認するか,コントラクトの発行者や管理者などを信用するかのどちからくらいしかありません.ほとんどの人は後者になるでしょう.
「システム外での作品の不正取引」に関してはNFT 発行者たち,たとえばクリエイターやギャラリー等のエージェントや権利管理団体,などが想定される不正主体です.たとえば,ある一つの作品を複数の NFT にして別々のプラットフォームで販売するなどは簡単にできます.プラットフォームAで NFT を買った人はそれが唯一の作品だと思っていたら,同じものがプラットフォームBでも売っていた,あるいはプラットフォームに乗せずにクローズドに自サイトで直売されていた,という類のことです.
クリエイター本人が不正をすることも無いわけではなく,たとえば従来の物品作品などでも,本来は存在しないはずのエディションが見つかる,つまりエディション外のものを作者が売ってしまうことは実際にありますし,APや譲渡品などが流出して転売されることもあります.第三者による作品や権利運用の場合は,もっとエグい話を聞くこともあります.また,最近のNFTバブルで目立っていたのは,無関係な誰かが他の作家の作品をコピーして勝手に NFT を発行して販売することです.他にもいろいろとありますが,要は贋作を流通させたり不正取引はいくらでもできるし,されているということです.
ですから,NFT は色々なものを信用しないと成り立たないものだと分かると思います.ブロックチェーンで発行されたトークンだから安全に運用できる,贋作対策になる,などというのはNFTでビジネスをしたいプラットフォーマーなどの受益者たちが流布している迷信です.結局は人間がつくったり管理するものだということです.NFTとして信用できるのは限定的な領域で,自分の作品が大事であればそれが何であるかを自分で理解しなければなりません.)
近い将来,主要なアプリケーションの設計やブロックチェーン自体の変更が必要になると予想されます.その時には,おそらく多くの既存の NFT 発行者たちはシステムを維持できなくなり,ほとんどのアート作品が消えてしまうでしょう.アート資産として,現在の NTF は非常に短命なものになるはずです.
/*
ちなみに,物理的な作品を紐づけてブロックチェーン上で所有権や出所を管理するといっているアート資産管理のサービスも,同様の深刻な問題を抱えています.
*/
僕は自分の作品に責任を持つために,自分でコントラクトを書いてデプロイしています.もし何かあったら,僕が別の安全な機構に移行させます.コレクターはこの問題を心配する必要はありません.
(追記:まあ僕が早死にしたら終わりですよね


なぜハイブリッドか
最初はデジタル エディションのみの販売を考えていましたが,それはあまりいい考えではありませんでした.
現在は過渡期です.デジタル作品を取り巻く環境が,ある程度成熟するまでは,アーティストは物理メディアを販売する権利を放棄すべきではありません.
すでに OpenSea などでは,NFT として作品が販売されていますが,「実際に販売された価格」のほとんどは十分なものではありません.これは,NFT では従来のアート作品のフォーマットに比べて,アートとして満足させる体験を作れないこと,デジタルデータに高値をつけるコレクターが少ないこと,プロが積極的に参加できる環境になっていないことなどが理由として挙げられます.
アーティストが制作費を回収できなければ,NFT のメンテナンスを含めたプロとしての活動を維持できません.
デジタル作品のみの販売で,作品のコンセプト作りや調査,自身のアートの技術やスタイルの確立などのコストを回収するには,まだまだ時間がかかると結論づけました.
/*
正直なところ,「レアなデジタルデータを売る」というコンセプトは,スマートではないと思っています.(将来生まれるかもしれない)今までとは違うデジタル作品のエコシステムは,未来のアートに新たな持続性と自由を与えてくれると信じています.しかしアーティストは今,稼ぐ必要があり,その意味で NFT は出発点としては価値があるはずです.
また,ブロックチェーン分野のアートのディストリビューターやサービス プロバイダーたちは,前述した作品供給の維持に関する問題や,ほとんどのアーティストが利益を得られないことなどの,不都合な真実を隠しているように思います.
アーティストを含む参加者の多くは,不安定なシステムに作品の権利を長期的に拘束されることの本当のリスクを理解していないのではないでしょうか.
もしあなたがアートを愛するのなら,そのようなリスクを最終的に負うのは,仲介者ではなく,アーティストであることを知ってほしいと思います.
*/
しかし,映像やジェネラティヴのような動的な作品は,デジタル市場での販売が必要なので,この新しい分野は開拓すべきです.
僕は10年以上,アート&テクノロジーの分野で仕事をしてきましたが,新しいアートフォームのための市場がないことに悩んできました.
アート&テクノロジーは新しい分野だと誤解している人が多いですが,半世紀以上の歴史があるものです.すでに世界中にさまざまな優れたアーティスト,アートセンター,大学,賞,フェスティバルなどが存在しているにもかかわらず,標準的なマーケットが存在しないのです.この問題は,現代のアートシステムの構造的欠陥に起因しています.
経済領域での技術的なオープンスタンダードとなるブロックチェーンを含む分散台帳は,従来の権威に依存せずに,アートに連帯と発展の自由をもたらすはずです.
今後,NFT のようなデジタルアセットのエコシステムが成熟していくことを期待しています.だからこそ,僕は自らリスクを取ってコミットし,誇大広告ではなく,本当のリスクや可能性をアート関係者に伝えるべきだと考えています.
アーティストが新しいことを試すには,経済力が必要です.ハイブリッド エディションは,そのための現時点での解です.あなたの購入は,私のこの分野へのコミットメントへの投資になります.
まずは扱いやすいビジュアルアート作品から始めて,より高度な新しいアートフォームをサポートし,アーティストの視点でデジタルアート体験を高めることができる汎用的な手法を開発していきたいと思います.
…ああ,フィジカル エディションについて書くのを忘れていました.
言うまでもなく,この作品は非常にクオリティが高く満足していただけると思います.A0サイズのフィジカルプリントの解像度を再現できる液晶ディスプレイなどのデジタルメディアは今のところないので,(印刷でなければ実現しない)このエディションの細部には価値を見出しやすいでしょう.
ただし,物理的な作品の流動性は,データに比べて低いので注意が必要です.
買い方について
デジタル エディションは OpenSea にあります.
下記のウォレットで NFT を扱い,OpneSeaに接続してください.
- パソコンでは,ブラウザ拡張の MetaMask をインストールして,アクセスします.
- スマートフォンでは,アプリの TrustWallet や CoinbaseWallet をインストールして,アプリ内ブラウザからアクセスします.
- *ウォレットをインストールした後は、必ず12語~のリカバリーフレーズをバックアップしてください.それはウォレットのマスターキーです.それを失ってしまうと,あなたの資産は永遠に失われてしまいます.
支払い — Ether(=ETH, 暗号通貨のひとつ)またはクレジットカードが OpenSea で利用できます.(ただしクレジットカードの場合は5%の手数料が必要なので,可能であれば暗号取引所で Ether を入手することをお勧めします.)
A beginner’s guide:
How to Use OpenSea to Buy and Sell Crypto Collectibles
フィジカル エディションは,このオンラインショップで.
このショップの作品には,すべて Goh の署名と証明書がついています.
クレジットカードと以下の暗号通貨をご利用いただけます.
Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Monero, ZCash, Obyte, Beam, BNB Coin, TrueUSD, USDC, Stellar, ERC20-tokens such as DAI, BAT, BNT, ZRX, KNC, etc.
https://goh.works/post/9181/
Get Goh’s Works

Blueprint